1.馬車は不穏に揺れる
ガタガタと揺れる馬車の中、彼女はひとつ、大きなため息をついた。
「どうかなさいましたか、姫様?」
「なんでもないわ、ブリギッテ。覚悟はしていたけど、やっぱり乗り心地がひどいなって思っただけ」
姫様と呼ばれた彼女は、向かいに座る侍女に明るく屈託を告げた。
「ドニーに言って、少し遅く走ってもらいましょうか」
「いいえ、どうせ大して変わらないだろうし、……花嫁が遅れるわけにもいかないでしょう?」
ブリギッテは「そうですか?」と言うと、再び手元の本に目を落とした。
国境を越えてから、どのぐらい経っただろう。
彼女は隣国の王子に輿入れするのだ。
窓の外の景色も見飽きてしまった。どうせ街道なんて国を越えたところで大して変わらない。
(……覚悟してたとはいえ、ひどい揺れね)
決して裕福ではない国の第三王女として生まれた彼女=ユーディリアは、この紋章入りの箱馬車が、見かけとは違ってオンボロであることを十分承知していた。ドアの建てつけが悪く、下に押すようにしないと開かないことや、車軸が歪んで揺れがひどいということは、王家の人間ならば誰もが知っていることである。
だが、新調する予算などないことを、同じく王家の人間ならば十分承知しているのも確かだ。彼女が嫁ぐ先のセクリア王国は、鉱山資源が豊富なこともあり、裕福な国だった。花嫁に支払われた対価は相当なものだったと聞いているが、それでも、箱馬車の予算までは手が回らなかったのだ。
『この程度の揺れ、馬の上に比べればどうということはないじゃろう』
彼女の目の前に、鎧を着こんだ髭の老兵が現れる。
「バカ言わないで、将軍。わたしよりも妹達のことを心配しているのよ。それに用がないなら、今日一日は出て来ないでって言ったでしょ?」
向かいに座る侍女ブリギッテは、ちらりと視線を向けたが、その言葉が自分に向けられたものでないと知ると、再び読書を再開した。ブリギッテの目には将軍の姿は映っていない。ユーディリアの目にも、半分透けて映っている。
『まぁ、そう言うな。儂とて、政略結婚の道具にされるお前が、初日からボロを出すのは避けたいと思っておるよ。……ちぃと、不穏な気配がな。隠れて外を見てみぃ』
将軍に言われて外に視線を向けたユーディリアは、小さく悲鳴を上げた。
「何よ、これ……」
『囲まれているのぅ。御者も何とか振り切ろうとしているようじゃが、いかんせん、馬が悪い』
窓から見えるだけで三騎の騎馬が箱馬車に併走していた。逆側を見れば、そちらにも二騎ほど見える。
「ひ、姫様……」
ブリギッテも外の異変に気付いたのだろう、怯えたような声を上げた。
『統率がとれているし、何より服装からして軍馬じゃろう。花嫁を迎えるには、ちと乱暴じゃな』
「何をのん気なことを言ってるの、将軍! あの紋章には見覚えがないわ、リッキー?」
『は、はい、お嬢様。自分を呼びましたか?』
将軍の隣に、眼鏡のひょろりとした背格好の青年が、まるで霧を集めたかのように現れた。
「胸に紋章が見えるわ。どこのだか分かる?」
『え、あ、はい。獅子と、剣に絡まるバラの花……自分の記憶違いでなければ、西の大国ミレイスの紋です。部隊証までは良く見えないですけど』
(ミレイス?)
ユーディリアの国レ・セゾンから、嫁ぎ先のセクリアを挟んで反対側にある大国だ。そんな国の騎馬が、どうしてこんなところに……。
御者のドニーが馬にムチを当てたのだろう、ガタガタと揺れがひどくなった。このままでは、馬以前に馬車が危ない。ガタガタという音の中に、ギシギシという音が聞こえるのは、決して空耳ではないだろう。
「ドニー、馬車を止めて」
箱馬車の前方についている小窓を開けて声をかけるが、気が動転しているのか、御者には聞こえていないようだった。
「姫様、正気ですか?」
「この上もなく正気よ、ブリギッテ。このままじゃ馬車が壊れるのがオチよ。……ドニー、馬車を止めなさい!」
大きく張り上げた声が聞こえたのだろう、「しかし……」と風に乗って躊躇する様子が伺えた。
「何度も言わせないで、ドニー! 止めなさい! あなたはこの馬車を壊す気なの?」
ドニーが観念したように手綱を引いた。馬車の揺れが穏やかになり、やがて止まる。
『震えているぞ、怖いのか?』
「将軍は黙っていて。……いえ、もしかしたら力を借りるかもしれない。準備はしておいて」
『承知』
ユーディリアは両手を胸の前で組んで、小さく祈りの言葉を呟くと、その手を馬車のドアにかけた。
「姫様! 何をなさるのですか! いけません!」
ブリギッテの静止の声に、ユーディリアが震える声を絞り出した。
「――あなたとドニー、それにこの箱馬車を守るのよ」
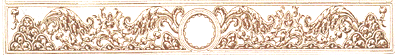
蒼天の下、優雅な箱馬車から純白の衣装をまとった彼女が姿を見せると、騎兵たちの口からため息が洩れた。
「ミレイスの方々とお見受けいたします。このような行為に至る理由をお聞かせ願えますか?」
ユーディリアは毅然として見えるように精一杯声を張り上げた。馬車から身を乗り出して、左手を乗降の時に使う手すりに添え、右手は拳を作ったまま、そこに並ぶ騎兵たちに視線を投げる。
『あ、あの、奥の黄色い徽章の人。自分の記憶が正しければ、第四皇子の、えーと、リカッロだよ』
リッキーがアワアワと指を差した先に、黒い軍馬に乗った青年がいた。
(何でそんな人が、ここにいるのよ?)
ユーディリアは、動揺を押し隠して、その王子に視線を定めた。
(機先を制する? それとも向こうの出方を待つ?)
『迷うぐらいなら、機先を制して主導権を握れ』
泰然とした将軍のアドバイスに、彼女は小さく頷いた。
「わたしの記憶違いでなければ、そちらにいらっしゃるのは、ミレイスの王子殿下でしょうか? どうしてこのような場所にいらっしゃるのか、お聞きしてもよろしいですか?」
視線の先にいる青年は、小さく肩を竦めると、馬を操り馬車に近づいて来た。自然と、馬車を取り囲む騎兵が道を開ける。
『ひの、ふの、みい、……八騎もおるのか。骨が折れるのぅ』
将軍が騎兵を数え、満足げに髭を撫でている様子が彼女の視界の端に映った。妙に楽しそうだ。
将軍に、不謹慎だと文句を言おうとして、止める。今は、居並ぶ騎兵に注目されている身なのだ。
「小国の王女にしちゃ、随分な度胸だな。神秘の国レ・セゾンのユーディリア姫?」
馬に乗ったまま、目の前にやって来たその男を、ユーディリアはまっすぐに見つめた。鉄錆色の短い髪、強い意志を持つ黒い瞳。右頬から顎にかけて走る刀傷が、その男が怖い人だと認識させた。
(えぇい、震えるな、足!)
「大国の王子にしては、随分乱暴な歓迎ですね。……リカッロ殿下?」
自信なさげに付け加えた名前に、目の前の青年が軽く眉を上げた。
「よく御存じなこった。……さて、この歓迎の理由だったな?」
リカッロはニヤリと笑う。
「残念ながら、お前の輿入れ先は、ほんの二日前に陥落した。オレ達は戦利品を回収しに来たってわけだ」
「陥落……」
ユーディリアの身体がぐらり、と傾いだが、手すりにもたれかかるようにして何とか立っていられた。
「お前にとっちゃ大した違いはねぇ。嫁ぐ先が変わるだけだ」
「嫁ぐ……先?」
「オレがこのままこの国を統治する。まぁ、正確に言えば『属国』だがな。お前の夫がオレに変わるだけだ。予定通りだろ?」
予定通り、という言葉に、騎兵の間でゲラゲラと笑いが起きる。
だが、同じ「予定通り」という言葉に、ユーディリアは活路を見出していた。
「予定通り、ですか」
いつの間にか下げていた視線を、再びリカッロに戻す。足を踏ん張り、気圧されないようにまっすぐに。
「では、このまま予定通りに城へ赴き、予定通りに明日の朝には、御者と侍女、そして箱馬車は我が国に戻るのですね?」
「それがそんなに重要なことか? もっと大事なことがあるんじゃねぇの?」
からかうようなリカッロを、ユーディリアはギッと睨みつけた。
「重要です。御者のドニーは十一歳と九歳の息子が帰りを待っていますし、侍女のブリギッテも来月に婚姻を控えている娘さんがいます。箱馬車は、まだ嫁いでいない妹達のために損なってはならないものですわ。……わたしは他国へ嫁ぐ身ですから、帰らなくても問題ありませんもの」
最後の言葉だけは、少し尻つぼみになってしまったが、言っていることは間違ってない、とユーディリアは返答を待つ。
「なるほど、つまんねーぐらいに王族の教科書的な答えだな。……まぁ、いい。予定通りに明日の朝には御者・侍女・箱馬車のセットを送り出してやろう。ついでに、うちからの使者をつけてな」
『なるほど、事後承諾を迫るつもりか。まぁ、使者がいるなら道中の安全も保障されるのではないか?』
将軍の言葉に、ユーディリアは小さく頷いた。
「ありがとうございます。……ドニー、そういうことだから、予定通りに城までお願いね」
いつの間にか御者台を下りていたドニーは、帽子を胸の前で握りしめ、涙をうるませていた。
「ひ、姫様ぁ~」
「そんな顔しないで。あなたのお仕事は、わたしを送り届けて、箱馬車を無事に戻すこと、でしょう?」
「は、はい」
ドニーはぎゅっと帽子をかぶり、御者台へ戻って行く。
「それでは、先導をお願いいたします」
軽くドレスの裾をつまみ、頭を下げると、ユーディリアは馬車の中に戻る。……軽い動作でドアを閉めるように見せかけつつ、耳障りな音がしないように力をこめて。
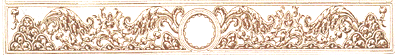
「姫様……、今のは本当のことなのでしょうか?」
中に戻るなり、ブリギッテが不安そうに尋ねてきた。
「さぁ、どうかしら? いくらミレイスの軍隊でも一国を落とすのに時間はかかるはずよね。―――あ、いけない!」
ユーディリアは御者席に繋がる小窓を叩く。
「ドニー、当初と違った道を通るようだったら、教えてちょうだい。また交渉するから」
「は、はい」
強張った声ながらも戻ってきた返事を確認すると、ユーディリアは両手を吐息で温めるように、口元へ持って行った。
まだ、セクリアが落ちたとこの目で確かめたわけではないから、今のドニーへの指示は的確だったと自分に言い聞かせる。嘘に踊らされて全く別の場所に行かれてはたまらない。
「姫様?」
「どうしよう。今になって怖くなってきちゃった。国王陛下や妃殿下はご無事なのかしら、ハルベルト様も……。もっとちゃんと確かめれば良かった」
セクリアの国王夫妻、そして婚約者のことを口にしたユーディリアに、ブリギッテは震える彼女の隣に座ると、その両手を包み込むように手を重ねた。
「大丈夫ですわ。リカッロ殿下の噂は聞いたことがあります。下町で生まれ育ち、王城に引き取られてからは、昔のツテを使って下町のならず者を集めて軍隊を一団作り上げたという話です。粗野に見えますが、大変頭の切れる方なのでしょう。ですから―――」
「ですから?」
「箱入りの姫様に疑われるような嘘はつかないと思います」
「ブリギッテ、あなたはこの国が攻め落とされたと思うのね」
「……はい、残念ながら」
「奇遇ね。わたしもそう思うわ。だからこそ、これからのことを考えて、ちゃんと動かなきゃいけない。だからこそ、震えが止まらないの」
「姫様。姫様に助けられた身でこんなことを言って良いか悩みますが、どうか、普通の姫君としてお過ごしください」
「分かっているわ。人目のある所では彼らと直接話さないように気を付ける」
「……おいたわしい。姫様は決して無能ではないのに、どうして外に嫁ぐようなことに」
「異能があっても、使えなきゃ無能と一緒よ」
神秘の国レ・セゾン。
貧乏小国でありながら、その歴史を支えてきたのは、ひとえに王族の異能の賜物である。神の血を受け継ぐとも、化け物との混ざりものとも言われているが、真相は分からない。
過去には読心、未来視、念力など、力の強い者が生まれている。当代国王であるユーディリアの父もその例に洩れず、触れている相手と心話ができる。密談にはうってつけだ。
異能もあって、周辺国からは畏怖の目で見られているが、その内実は貧乏国以外の何物でもない。その異能を発揮すれば、金に苦労しないことも可能なはずだ。周辺国とうまく付き合っていくために、金は敢えて無視しているという見方もあるが、真実は歴代国王しか知らない。
王族に異能が生まれると言っても、その能力は質・量ともに様々で、全く異能が顕現しない者もいれば、とても役に立ちそうもない能力を持つ者もいる。遠くの出来事を見通す千里眼は過去に何人も出ているが、隣の部屋ぐらいしか見れない者もいれば、それこそ国境を越えて目を飛ばすことのできる者もいる。
ユーディリアの異能は、幽霊と話すことと、その力を借りることだった。彼女の周囲には三人の幽霊がいて、それぞれ得意分野を持っている。彼女以外に彼らは見えず、声も聞こえない。体を貸して話しても、本当にそれが幽霊なのかは分からない。また三人の得意分野も、決して異能の域とは呼べないため、ユーディリアは『無能』扱いされ、外に嫁ぐことになったのだ。異能持ちであれば、国から出されることはない。
「ねぇ、ブリギッテ。わたしはあの王子に嫁ぐことになるのかしら」
「あの王子殿下はそうおっしゃってましたね。……不安、ですか」
「よく分からないわ。ハルベルト様だって別に好きってわけじゃないし、そりゃ、国王夫妻は良い方だけど、結局、国同士の契約でしょう? そこはいいの。むしろ近い国だから、事前に何度も訪問することができて良かったってぐらい。……わたしが心配しているのは、国の内情が不安定になってるだろう、ってことと、お父様がどう判断するかってことよ」
ブリギッテは少し考える間を持たせるように、ユーディリアの手を撫でさすった。
「確かに、攻め落とされたばかりとあっては、国中が不安定になっているでしょう。そこは、リカッロ殿下のお力次第ですわ。陛下のお考えは、正直、検討がつきませんが、リカッロ殿下の出される使者次第かと」
「そうね、どうせセクリアからの持参金は前払いでもらっちゃってるしね」
ようやく笑みを見せたユーディリアにブリギッテがあからさまにホッとした顔をした。
「ごめんなさい。今考えても仕方がないわよね。こういうのは、臨機応変でいかなきゃ」
「その調子です、姫様。……そろそろ、ヴェールをお付けいたしましょう」
「結婚式するかどうかも分からないのに?」
「表情は見えない方がよろしいでしょう?」
「そういうものかしら?」
「しばらくは悲壮な花嫁を演じていた方がよろしいでしょう。嫁ぎ先を奪われた悲運の王女、いかがです?」
「素敵、ブリギッテ。その案ナイスだわ!」
ユーディリアは感激の声を上げ、侍女に抱きついた。
「馬車がこんなにが揺れなければ化粧と髪も直したかったのですけれど、仕方ないですわね」
ブリギッテも両腕を姫の背に伸ばし、抱きしめる。
「そうね、仕方ないわね」
石を踏んだのか、馬車がガタンッと一層揺れた。途端に、馬車の中の二人は声を上げて笑った。