バケモノ姫の謁見騒動
「おい、ユーリ。本当に大丈夫なんだろうな?」
「大丈夫よ、ただ座ってるだけなんだし。心配が過ぎるんじゃない?」
「……お前、自分の体調自覚してるか? 将軍にだって、そればっかりはどうにもなんねぇだろ」
「謁見だけでしょ? しかもレ・セゾンからの使者なのに、何を心配しろって言うの?」
「いや、まぁ、それはそうだが」
言い合いをしながら、それでもリカッロは隣を歩く妻の腰に手を添えてゆっくりと歩く。ぽっこりと膨れたお腹を抱えるユーリは、心配する彼をこそばゆい気持ちで見上げた。
「ね、わたしは大丈夫よ。だから、そんなに心配しないで。それに、わたしだって、この国の王妃なのよ? 自国からの使者すらもてなせなかったら、お父様に呆れられちゃうわ」
「……分かった」
悪阻のひどい時期に、ユーリが食べ物を受け付けずにげっそりとしていたのが堪えたのか、最近のリカッロはやたらと心配性になってしまっていた。別にそこまで気にしなくても、と本人は思っているが、どうやら十五の頃に亡くした母と重ねてしまっているらしい。長年の片腕であるボタニカからの情報だが、そういう話は直接本人から聞きたいのに、リカッロはユーリになかなか弱みを見せないので困っている。
「ほら、そんな顔しないで。早くしないと使者を待たせてしまうでしょ?」
「あぁ」
それでもゆっくりとした足取りで進む二人を、近衛やすれ違う文官が微笑ましく見守っていた。
謁見のための小部屋には、既に使者が控えていた。二人が席につくまで頭を下げていたため、その顔は分からない。わざわざ余人を交えず、という指定だったため、部屋の中には使者の他には二人ほど信頼できる者しか同席していなかった。
(今回の使者はどなたかしら? 金髪、ということはマクラウド卿ではないわよね)
ユーリは侍女が整えてくれた絶妙な位置のクッションに感謝しながら、使者の頭を見つめた。少し、白髪が混じっているように見えるから、それなりの年を重ねているのだろう。はたして、自分の知り合いだろうかと考えて……その使者が頭を上げた途端に、ピシリ、と凍りついた。
「ダイアン……叔父様?」
「国王陛下、王妃殿下におかれましては、ご機嫌うるわしゅう」
使者の視線はまっすぐにリカッロに向けられている。ユーリの知る叔父とは違い、真面目な表情で、真面目に使者としての役割を果たす彼は、別人にも見えた。否、別人だと思いたかった。
「我が国にユーディリア様ご懐妊の報がもたらされた折には、王族の皆様ご一同、とてもお喜びでいらっしゃいました。ご生誕の暁には、我が国からも祝いの品々を贈らせていただきたく―――」
つらつらと口上を述べる使者は、ユーリの様子に気がついているだろうに、その口を閉じることはしない。ただ、決められた言葉を重ねていく。リカッロは、初めて見る使者の顔を注意深く伺いながら、手元に差し出された親書に注意を向けた。
「この、元老院というのは?」
リカッロの問い掛けに、ユーリは大きく体を震わせた。
「陛下はご存知でしょう。我が国の神秘の力が決してまやかしなどではないと。元老院は主に王族の異能を判定しております。ユーディリア様も、元老院の判断によって外へ嫁すことが定められました」
「そうなのか、ユーリ? ……どうした、やはり具合が」
「……いいえ、大丈夫です。リカッロ」
青い顔をして小刻みに震えるユーリの指先はすっかり冷たくなっていた。
「使者、様は、この城に滞在されます、の?」
「はい。一室を頂いておりますので。王族の皆様方よりユーディリア様宛てに手紙も預かっております。よろしければこの謁見の後で、皆様方の近況を話しながら、と思ったのですが、気分が優れないのであれば、仕方ありませんね」
「ユーリ。いいから、もうお前は下がれ。本当に顔色が悪いぞ」
リカッロは警備の一人に合図を送り、部屋まで護衛するよう告げる。
「だめです。待って、叔父様!」
「かわいいユーリ。公式な国の使者として来ているのに、君が心配するようなことはないよ」
使者としての顔を一瞬だけ崩し、へらり、と笑って見せた彼に、ユーリはギュッと唇を噛み締めた。
「妃殿下、どうぞ」
「待って、待ってください。叔父様、……奥様も同伴されていらっしゃいますの?」
「ミラさんは一緒じゃないよ。あぁ、でも、城下には来ているから、できればミラさんの歌を聞いてあげて欲しいかな」
「! お断りいたします!」
声を荒げたユーリは、そのまま卒倒しそうになるところを、兵に支えられるようにして退室していった。
「……どういった思惑があるか知らないが、あまり妻を刺激しないでいただきたいものだ」
「それは申し訳ございません。久々に会ったというのに、変わりない姪を見て、つい嬉しくなってしまいまして」
「姪?」
「その話はもうよろしいでしょう。あぁ、そちらの書状についてですが―――」
ユーディリアの叔父だというその使者は、その後、リカッロの揺さぶりをのらりくらりと受け流し、使者としての仕事を全うし続けて、彼に何も情報を与えようとはしなかった。
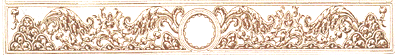
「妃殿下は何かに脅えられるようにしていらっしゃって……」
ユーリ付きの侍女から様子を聞いたリカッロだったが、何かと仕事が立て込んでいたため、結局、彼女の顔を見ることができたのは、それらを全て片付けた、深夜に近い時間帯であった。
「ユーリ?」
寝室に入ると、ごそごそと衣擦れの音がして、寝台から妻が顔を覗かせてきた。
「お帰りなさいませ、リカッロ」
寝台から下りようとするのを手で制し、その額に軽く口付ける。
「まだ、顔色が優れないな。大丈夫か?」
「……大丈夫、ですわ」
大丈夫と告げたその口で、ユーリはそっと腕を伸ばしてリカッロに抱きついた。いつになく甘えるような行動に、そっと背中に手を回してやれば、ほう、と小さな溜め息が彼の胸をくすぐった。
「叔父、と言っていたが、あの使者も王族なのか?」
「……えぇ、そうです」
「それならば、異能も?」
「それは―――」
ユーリは逡巡した。レ・セゾンの王族が何かしらの異能を持つことは、リカッロも知っていることである。だが、その異能の内容を話すことは、国を売ることに他ならない。ユーリは既に他国に嫁したといっても、母国は母国だ。友好的な関係を築いているが、それもいつまで保つかなんて、誰にも分からない。
だが、ユーリが危惧しているのは、その異能に深く関わることだ。リカッロにも注意をしてもらう必要があるし、それなら尚、事情をきちんと話すべきだろう。
「ダイアン叔父様は……」
『当人が来たぞ。バルコニーだ』
寝室では滅多に姿を見せない将軍が、ユーリに告げる。突然、言葉を切ってしまった彼女の背を、リカッロはそっと撫でた。
「リカッロ、その、将軍が、バルコニーに、いえ、バルコニーに居るのは叔父様で」
「落ち着け」
「でも、あぁ、叔父様が来られないわけがないの。でも、どうしたらいいの。叔父様はきっと、この子を―――」
「ユーリ。大丈夫だ。……バルコニーだな。オレが見て来よう」
ぎゅっとユーリを力強く抱きしめると、リカッロはそっと体を離した。だが、彼の上衣の裾を、ユーリが握って離さない。
「ユーリ?」
「だめです。だめ。だって叔父様は―――」
涙を浮かべて首を横に振るユーリの耳に、「お邪魔するよー」と能天気な声が届いた。
「夫婦水入らずのところゴメンね、邪魔するよ」
無遠慮にやって来たのは、昼間使者としてまみえた男だった。だが、その表情はすっかり緩み、へらへらと笑顔を浮かべて手を振る。
「貴様、誰の許可を得てここへ入って来た」
「んー? うわぁ、怖い怖い。勘弁してよ。大国ミレイスの四男坊とかさ、いろんな逸話があり過ぎて、ほんっと怖いんだから」
両手を上げて降参ポーズをしたまま、使者=ダイアンはどかりと長椅子に腰を下ろした。
「さて国王陛下、妃殿下。こっから本当に内密の話をしたいんだけど、覚悟はいいかな?」
「てめぇ、何我が物顔で座ってやがる」
「あぁ、ごめんごめん。でも、君としては、その方が楽じゃないのかな? 座ってる侵入者の方がたたっ切りやすいでしょ」
自分の命なのに、軽々しく言い放つ彼に、リカッロは違和感を覚えた。王族にしては、場慣れし過ぎている。
「叔父様は、諜報とか、潜入とか、得意なんです……」
まだ彼の上衣の裾を掴んだままのユーリが囁いた。
「ユーリ、大丈夫か?」
「大丈夫です。―――叔父様、夫婦の寝室に入り込むなんて、奥様に会ったら言いつけちゃいますよ!」
大きく声を張り上げた彼女は、リカッロの腕を頼って立ち上がると、寝巻きの上からガウンを羽織った。
「うわぁ、すっかり厳しくなっちゃって。叔父さんは悲しいよ」
「ここまで忍んで来た、ということは、異能に関わるお話なのでしょう? ―――この、お腹の子の」
リカッロの腕を掴む手は、硬く強張っていた。そんなユーリの緊張を悟って、彼はそっと額に口付ける。
「そうだよ、かわいいユーリ。だから、ちょっと時間もらえるかな?」
「……リカッロ、少しだけ、いいですか?」
「そうだな。どうやら帰りそうにもねぇし」
姿を見せると、長椅子でくつろいでいたダイアンは、一層緩んだ表情を見せた。
「ユーリ、元気だったかい? あと、君の3人のお友達も」
「えぇ、この部屋へいらっしゃることも、将軍が教えてくれましたわ」
ユーリはリカッロに寄り添って、ダイアンの向かいに座る。
「叔父様は、この子に異能があれば、……消す、つもりなんですか?」
「そうだね。まぁ、異能の種類とその子の性別にもよるけど。周辺国に知らしめる、とか言いながら、他の国に有用な異能が出たらまずいって考える元老院は本当に面倒で困るね。まぁ、彼らもセクリアなら、とユーリの輿入れを認めたけど、最終的にミレイスの属国になっちゃったからねぇ」
まぁ、確かにあれは予想外だったけど、と笑う男からは、緊張の欠片も見えない。「消す」という無慈悲な言葉と目の前の男が無縁に思えて、リカッロは表には出さずに困惑していた。
「リカッロ。叔父様は自分の異能と特技を生かして諜報活動をしている人なんです。要人の暗殺も、でしたよね?」
「あれ、ユーリ、そこまで知ってたんだ。やだなぁ、あちこち転々としながら、場末の酒場でピアノを弾くだけのしがないおじさんなのにさ」
「ダイアン叔父様。半年ほど前、ミレイス本国に行きませんでしたか?」
「……」
ぴたりと黙ったダイアンに、ユーリはずっと抱えていた疑惑を確信に変える。
「リカッロ。半年前にハルベルト様がお亡くなりになったと言ってましたよね。あの時は、死因を教えてもらえませんでしたが、今、教えていただけませんか?」
「おい、ユーリ。まさか―――」
「死因を聞けば、判断ができます。……とても不自然な死に方を、していませんでしたか?」
ひょろりとしていて、とても「そんなこと」ができそうにないダイアンが、「あんな殺し方」をできるのか、とリカッロが唸る。だが、そこはレ・セゾンの異能の為せる業と考えれば納得できなくもなかった。
「だめだ。お前に聞かせられるような死に様じゃない」
たとえ恨みを持っている相手だとしても、元婚約者の無残な死に方を教えることはできなかった。ユーリもそうだが、何より胎教によくない。
「うーん、ユーリは本当に旦那のことを信頼してるんだね。これなら期待してもいいかな」
「何だと?」
「一国の主だとしても、君の治める地は『属国』だ。君は本国に神秘の力を隠し通せるかな?」
ダイアンの言葉に、ようやく彼が訪問して来た意味を知ったリカッロは、不敵に微笑んだ。
「なるほど。大国であるミレイスに、迂闊に神秘の力を使われたくないってことか。―――当たり前に決まってんだろ。ユーリも、腹の子も、オレのもんだ。バカ親父やクソ兄どもに奪われてたまるか」
「あぁ、不仲っぷりも、君の不遇っぷりも聞いてるよ。……そうだね。君が、親兄弟に逆らってまで守るというなら、しばらくは様子を見るよ」
へらへらした笑みではなく、にっこりとユーリに笑みを向けたダイアンは、まっすぐ二人に向き直った。
「元老院からうるさく言われてこっちに来たけどね、正直なところ、君らの覚悟を知りたかったんだ」
「……ダイアン叔父様?」
「あぁ、ユーリの推理は合ってるよ。ほら、あの元王子は、どうにも口も頭も腰も軽かったからさ。あんな調子でユーリの異能をペラペラ喋られても困るんだ」
「あれを……? 待て、それなりに警護もついていたはずだし、何よりもあの死因は―――」
ダイアンは笑みを深めてリカッロの追及を封じた。
「そうそう、生まれた子の異能に手が負えなかったら、いつでも呼んで欲しいな。ミラさんなら、何とかできると思うから」
「それは、この子の異能をなくす、ということですか?」
「さぁ? 状況によるとしか言えないかな」
へらり、とすっかり元の調子に戻ったダイアンは、「よっこいせ」と立ち上がった。
「じゃ、そろそろお暇するよ。ユーリ、君も元気そうだし、旦那さんと仲がいいようで何よりだ」
「……ダイアン叔父様も、お元気そうで何よりでしたわ」
「うん。あぁ、純粋にミラさんの歌を聞かせたい気持ちに代わりはないんだよ? しばらくはいるから、お忍びとかで城下においでよ」
「……身重なので、お忍びはできません」
「あぁ、そっか。じゃ、出産してからかな? ミラさん子守唄も上手だから、教えてもらいなよ」
「歌はベリンダがいるので大丈夫です」
「うーん、そっかぁ……」
残念、と腕を組みながら、ダイアンはバルコニーの方へと歩いて行った。
「おい、そっちから帰るのか?」
「あぁ、誰かに見つかっても面倒だしね? 大丈夫、慣れてるからさ」
ひらひらと手を振ると、ダイアンはそのままバルコニーへと出て行ってしまった。
「ユーリ?」
「はい」
「大丈夫か?」
ユーリは思わず口に手を当てて笑ってしまう。
「ごめんなさい、リカッロ。だって、最近その言葉ばっかりで」
妊娠が分かってから、とりわけお腹が目立つようになってからは、リカッロは日に一度は「大丈夫か」と口にする。意地の悪い彼を知るだけに、心配していることは分かっても、何だかこそばゆい。
「お前は……」
リカッロの手が伸び、ユーリのふっくらとした頬をむにっとつまむ。
「いひゃいでふ、ひはっろ」
「……ったく、異能がらみの話でも、お前がぽんぽん進めるな」
「れもれすね、おひはまは」
「何を言ってるのか分からん」
「ほれなら、はなひへくらはい」
恨めしげに夫を見上げるが、リカッロは、ふにふにと軟らかい頬を堪能しているようで、なかなか離してはくれなかった。
ようやく彼の手が離れた時には、ユーリの頬がじんじんと痛みを訴えていた。
「お前も、この子どもも、ちゃんと守るから、安心しろ」
「リカッロ。わたしも貴方を守りますから、お互い様です」
「お前に守られるとか……。いや、ユーリは暴走するから、逆に心配だ。やめろ」
ユーリの体を引き寄せたリカッロは、そのまま自分の顔を彼女の金の髪に埋めた。鼻腔をくすぐる彼女の香りに劣情を催しそうになるが、そこはぐっと堪える。
「別に暴走なんて、しませんから」
「前科があるのに信用できるか」
自分の手で元婚約者をやりこめようとしたり、浮気を疑われたり、愛人を勧められたりと、暴走の度にその始末をつけてきたリカッロは、彼女を宥めるようにそっと背中を撫でる。
「リカッロ」
「なんだ」
「……この子に、どんな異能があっても」
「大丈夫だ。オレとお前の子だろうが。見捨てねぇし放り出さねぇしきっちり教育してやる」
ユーリの不安を断ち切るように即座に断言したリカッロを、彼女はぎゅうっと抱きしめた。
「ありがとう、リカッロ」
「そこはもっと、ちゃんと感謝を表せよ。―――ほら」
「ん……」
リカッロを支えにしながら、少し背伸びしたユーリは、促されるままに彼の唇に自分の唇を重ねた。何回やっても、どうしても慣れずにぎこちなく重ねるだけになってしまう。
「足りねぇが、まぁいいか」
ガウンを脱がせ、薄い寝衣姿のユーリの首筋に舌を這わせると、そのまま彼女の肌を堪能する。胸元にきつく吸い付いて所有印を刻んだところで、リカッロは意地の悪い笑みを浮かべた。
「ここはすっかり張ってるな」
「……妊婦なんですから、当然です」
「オレのだったのに、すっかり子どものために作り変えられちまって」
「元々、わたしの体です!」
「久々にユーリを味わうか」
「ちょ、ちょっと、リカッロ!?」
「大丈夫大丈夫。子持ちのヤツらに教わったから、安心しろ」
「安心できるわけが、ないじゃないですか!」
ここしばらく寝過ごすことのなかった王妃が、その翌日は昼過ぎまで寝台から出てこられなかったのは、当然の流れだった。