緋色の君
“Nothing is beautiful than the bloody murder”
「何よ……これ」
私はたった一件の電子メールに、とてもげんなりとした。イタ電ならぬイタメールとでも言おうか。はっきり言って気持ち悪いシロモノである。
「さよーなら。ゴミ箱行きね」
そのメールをゴミ箱に移動させ、私はパソコンの電源を落とした。
「まったく、人間的にどーかと思うね」
一人暮らしのせいで独り言が多くなったもんだけど……と呟きながら、風呂を入れる。夕食を作る。そして……、ヒマになり、ちょっとだけ好奇心がはたらく。
「murderって、なんだっけ?」
テレビをつけることも忘れ、英和辞書を探してみる。
『murder』――それは見たことがある単語に思えた。
「…え、と。あった。マーダーって読むのかな、これ? ……殺人者?」
私はジー●アス英和辞典をそそくさとしまうと、その日はさっさと寝た。
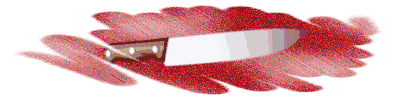
「はぁー、ただいま」
今日は古文の先生がイヤな感じだった、と思いながら、いつもの習慣でメールのチェックをする。
“Nobody is perfect except for murder”
そして、何も思わずにそのメールは「ゴミ箱」に捨てた。
だが、三日、四日とその”murder”の文字が含まれたメールが続くと、いいかげん、このヒマ人にもムカッ腹がたってきた。だけど『殺人者』なんて、どう聞いてもいい言葉じゃない。
「いっそのこと警察に通報してやろうかしら」
と、そこまで思い立ち、ふと、この差出人に心当たりがないかと見る。
“A SENSE OF GUILT”
(……めちゃくちゃハンドル名よね、これって……?)
日本語に直すと『罪の意識』? ははは、相当イッちゃってる人だわ。あぁ、日本人とも限らないわよね。英語でしかメールは届いてないんだから。
「ま、いっか」
そして、何となく一週間が過ぎ、とうとうゴミ箱の中に”murder”シリーズのメールがたまってしまったのである。
「笑えるし、誰かに見せよーかなぁ」
もはや単なる話のタネでしか使い道のないモノである。彼氏もなく、特にやりたいこともない人間は暇こそが大敵なのだ。そして、十一通目の”murder”シリーズをチェックすべく、ログインする。
“血に染まった殺人者ほど美しいものはない。”
「おや、日本人だったのか」
思うことはそれだけであった。念のためハンドルをチェックすると”A SENSE OF GUILT”……何ら変わっていない。
「やっぱり、後でひー子さんたちに見せよーかしら」
高校の友人の名前を呟きながら、そのメールもやっぱりゴミ箱行きなのであった。
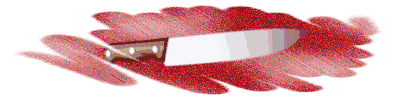
「えー? それってヤバくない?」
「そぉ? 別にぃ……」
昼休み、私はとうとう友人にその話をする。
「だって、藤ちゃん。それ変態さんだよォ? ヤラれっちゃうよォ……」
「そーそー、それとも英語使ってっから、インテリっぽいとか思ってる?」
「藤ちゃんって、こーゆーのに危険イシキないよねー」
悪友三人にたたみかけられて、私はつい圧倒される。ちなみに、沢木藤子というのが私の名前。「サワキトウコ」と読む。
「藤ちゃん、警察に言おうよォ。だって藤ちゃんも女の子何だからァ」
ぽやんとした口調ですごいことを言うこいつがひー子。久子という名前だけど、自分の名前をひー子と言い張るから、本当にひー子と呼ばれている。
「トーコ。まじにヤバくねぇ? 今回ばっかりはひー子の言うとおりだと思うよ?」
これがサツキ。ちょっとグレてるけど、根はいい人間なの。生徒指導室の常連さんだけどね。
「藤ちゃん、今度それ見せなよ? 学校中に張り出してやっからさぁ。ひゃはは」
ミカン……もとい、みえこ。本人がミカンが好きだってゆーんで、ミカンというあだ名が付いた。
「ま、いーのよ。どーせ、メールしか来ないんだから」
「本人来たらヤバいって。一人暮らしだろ、藤ちゃん」
「そーそー、ミカンの言うとおり! 事故で両親のいないアンタだもんね。……あ、これ貸したげる」
サツキが鞄からスタンガンを取り出した。
「あ、じゃぁ、あたしもォ」
ひー子が防犯ベルを出して、私に握らせた。
「……ん、じゃ、これ」
ミカンがもじもじと出したそれは「うすうす」。コンドーさんであった……。ちょっとだけ、ちょっとだけミカンの分からない行動に頭がくらくらした。
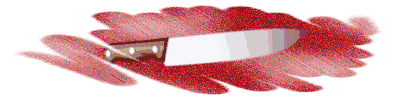
“君は美しい。なぜなら君は人殺しだから。醜い者をDELETEした美しい人”
さすがにこれは、誰にも相談できなかった。あまりにもショッキングな内容で。まさか、もし、これが本当だったらシャレんならん。
私は、そのメールが来た日から”murder”メールのことは高校で話さなくなった。
(殺人者……私が?)
(そんなこと、あるワケないじゃん。変態さんの言うことなんて真に受けちゃダメだよ)
不安感をかき立てるそのメールは続々と届く。そしてとうとう具体的なメールが届いた。
“醜い男は城坂新聞に死に恥をさらす。今日できっかり一年目”
城坂新聞は、この地域のみの地方紙である。つまりは私の住所が知られている、と。私はワケあって両親と死に別れ、一人で暮らしている。そんなトコに、変質者なんかが訪問してきたら……
私は震える自分の肩を抱いた。とうとう、その翌日は学校を休んでしまった。
――そして、メールが来た。
“炭は元々誰のものか。油は誰が持ってきたのか。炭は踊った”
私はもういてもたってもいられず、図書館へ急いだ。
「すいません! 二〇〇〇年の五月……七日の新聞が見たいんですけど!」
職員は、もう少し大きい中央図書館へ行くようにすすめてくれた。ここには保管していないから、と。
(私……何やってんだろ)
いったい何を調べようと言うのか。だが、それでも足は中央図書館へ向かってしまうのだった。
「はい、少々お待ち下さい」
書庫の方へと行くそこの職員の背中を見送りながら、私はぼんやり考えていた。
――去年の五月に何があったというのだろう?
――メールの主は何を知っているというのだろう?
(何で……私、信じてるんだろ?)
一瞬、帰ろうかとも思うが、それだと新聞を取りに行っている図書館員に申し訳ない気がする。
(どーせ嘘だって分かるんだから、いーじゃん)
「はい、どうぞごゆっくり」
新聞を渡され、私は隅から隅まで、なめるように見た。
『男性死亡・火』
その条件に当てはまる記事はたった一つ。そう一つだけあった。
「○○町で火事。男性一名が死亡」
詳しく記事を見ると、どうやらタバコの不始末と言うことで話はついているらしかった。河川敷でタバコをふかしていたところ、そこに放置してあったガソリンに引火して炎に巻かれたらしい。そこからはガソリン入りのポリタンクを放置したままにしておいた河川敷の管理問題に話が発展している。
男性の名前は「石井 純」。聞き覚えはないし、42歳という年齢から見ても、自分との接点はないように思われる。
(つまりは杞憂に終わったってことか)
私は新聞を帰し、自分の家へ。すっきりした気分で帰った。もう、最初の頃のような気持ちで無視できそうだ。あの”murder”シリーズは。
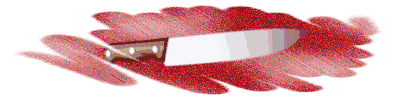
“ドラム缶に油を入れてキャンプファイヤーを。油はもちろん人間産”
“殺人の記憶は泡沫に消える”
(ベタな内容が続いて、いいかげん飽きるよな~)
特に後者は、罪の意識や不安をかき立てる文句みたいだ。
「あーぁ、いい加減にケーサツに通報しちゃおっかなー」
そう思い始めた頃、一通の手紙が届いた。差出人の書いていない白い封筒。
「誰からだろ、ばーちゃんからかな……」
ビリリ、と私は封を切って中身を取り出した。
「……!」
夜闇を照らす燃えさかる人影。それを見て笑う私がいた。
“You’re a murder”
写真の裏には、赤いペンでそう書かれていた。
「い……いやぁ」
座り込む私の頭の中で、グルグルと「殺人者」の単語が巡る。見られている、知られている。……私の知らない記憶も全て―――
プルルルルル……
私はびくっと体を強ばらせた。電話、誰からの?
プルルルルル……
呆然とする私を急かすように、電話のベルが鳴り響く。私はのろのろとした動作で受話器をあげた。
「はい。――沢木ですが」
『コンにチワ、ヒトごろシさン』
テレビで聞くような、音声を変えた声。さらに抑揚のない声。
『でンワ、キッちゃダめダヨ。ホんトノコとガシリたけれバネ』
どくん、と心臓が跳ね上がる。ようやく麻痺していた心が動き始めた。状況を把握できる。
「……警察に通報するわ」
『キみモつかマルノに?』
「……」
『ひとゴロしサん。キみは、ミニクいオとこヲコろししタヨね?』
「……私は誰も殺していない。あなたの勝手な妄想よ」
不安な自分を振りきるような言葉。私は決して誰も殺していない。
『ショウコをミセてアゲるよ。コンや11じ、カせんジキのごるフじョウへオいで。ドこノコとだカハイわなクテモワカるよネ……プツッ、ツーツーツー』
(今夜11時?)
切れた受話器を手に、私の心は揺れていた。
行くべきか、行かざるべきか。行かない方がいいと思う。常識とか理性とかで考えれば、そうなる。相手はタチの悪いストーカーなんだから。でも―――行った方がいいと、知りたいと思う。『証拠』が怖い。
私は時計を見た。午後九時半。私は黒いジャンパーを取り出した。そして、引き出しを開け、スタンガンと防犯ベルを取り出した。
(サツキとひー子に感謝しなくちゃね)
ミカンのくれた『うすうす』はもちろん引き出しの奥深くにある。
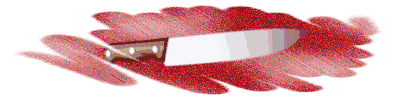
キィィッ
午後一〇時五〇分。とうとう例の場所まで来てしまった。私はチャリを止め、警戒しながら河川敷に降りていく。少し離れたところに赤いものが見えた。
近づいてみると、それは灯油を入れる、赤いポリタンクだった。
「まさか、これが証拠ってワケ?」
小さな声で呟く。時計を見る。10時59分。
「帰ろーかな」
そう呟いた時、背中にどんと衝撃が来る。あまりの勢いに、私は前からうつぶせに倒れた。その上に何かがのしかかってくる。
「な……」
ズボン越しに、何か、イヤな感触が伝わってきた。足をばたつかせるが、振りほどくこともできない。誰か人間に撫でられてると気づいたとき、カッと顔が熱くなった。
めちゃくちゃに暴れて、肘が相手のあばらあたりに入ったらしく、力のゆるんだ所を、私はぐっと振り切って立ち上がった。遠くの街灯に照らされた知らない顔。20代後半ぐらいの、普通っぽい人。
じりじりと後ずさっているところに、奴は懐中電灯を私の顔に向けた。慌てて目をつぶると、再び衝撃。受け身もできぬまま、後ろに倒れる。運の悪いことに、頭がぐらぐらとして―――
―――気を失っていたのはそう長い時間ではなかったらしい。奴は私を組み敷いて服を脱がそうとしていて、私が目を覚ましたことには気づいていない。
(えいっ!)
心の中で気合いの声をあげ、私は奴の頭をガンッと殴った。奴は低く呻いて頭を抱える。私は奴の体の下から這い出し、体勢を整えた。
「どうして……」
服を整える私の耳に、奴のものらしき声が届いた。
「どうして! ……あんな醜いヤツにはヤらせたのに!」
(――――)
「あんなヤツに! 僕の方がずっと君を見ていたのに! 僕の方が君を愛しているのに!」
鳥肌が立った。まさか、こんなイヤな言葉を私が聞くはめになるとは思わなかった。危険。そう、日頃使いそうで使わない言葉……狂っている。
「あんなヤツには素直にやらせたのに!」
何かを投げつけられる。バサッと音をたてたそれは紙束。私の授業中の、友達と一緒の、部屋の中の、そして――――
「思い出したか、この売女!」
新聞の記事がぐるぐる回る。殺されたのは42歳の男性。そして、この写真で私に乱暴、レイプしているのも中年の男性。
「僕は誰にも言わなかったのに! 君を守って来たのに!」
泣いているのか笑っているのか、ただ喚く奴の声に記憶が戻る。忌まわしい記憶。石井……純? 名前なんてどうだっていい……。
あの男は私を―――― 私はあの男を――――
(――――ドウシタ?)
フラッシュバック。赤いポリタンク。炎の中で踊る黒いモノ。
私の目の端に『赤いポリタンク』が映った。私の中の誰かが囁く。
(再現スレバイイ)
赤いポリタンクの中の液体を、奴にぶちまける。バシャッと音がして、きついガソリンの臭いが鼻を突く。
奴が振り向く。恐怖に脅えた顔。
丁寧に用意してあったマッチ。私は半ば笑いながら、それを擦る。灯るのは赤いモノ。
奴が逃げようともがく。足下がガソリンで滑って上手くいかない。
「ヤらせてくれと頼んだのは誰だったかしら?」
赤く炎が、夜空まで照らす。聞くのも耐えない悲鳴。そのくせ、綺麗に踊る黒い人影。
マッチを炎に投げ込む。黒く踊るモノに当たる。ポリタンクも投げ込む。それは溶けて、黒い人影に服を着せる。赤いドレス。
――――私は自分の服を着ると、チャリをこいで帰る。家に帰ったら、服を一式捨てなきゃ。あの時のように。そして、また新しい服を買おう。大丈夫、お金なら、まだある。両親の残してくれた保険金。私が勝ち取った保険金。
――――そしてまた記憶を閉ざすのだ。今度こそ二度と思い出さないようにと。