夏向きの話
その日はとてもイヤな予感のする日だった。
普通に歩いていたら、すぐ横にハトの糞が落ちてきた。間一髪だった。
しばらく歩いていくと、行く手を阻むように、野良猫がウンチをしていた。臭かった。
そして、それを避けたところで、手のひらにすっぽりおさまるぐらいの木箱を見つけた。最初は厚めのマッチ箱かと思った。実際、軽く振ってみるとカラカラと音がした。
それがいったい何なのかは分からなかったが、僕はそれをポケットに突っ込んだ。
家に帰ってから改めて木箱を見るが、中に何が入っているか分からないし、カラカラと音がするだけで、何もいいことがない。
僕は少し考え、窓辺に置いた。
窓辺に置いたことに、たいして意味はない。ただ、日にあてたら多少は木がもろくなるかと思って見ただけだ。ハンマーか何かで壊しても良かったが、それもつまらない。元々、何か興に乗るようなものを探していたから。
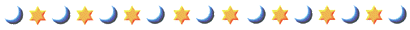
毎日毎日が同じようなことの繰り返しで、いささか僕は生きることにも飽きて来ていた。
珍しいこともなく、ただあるがままに過ぎて行く日々。
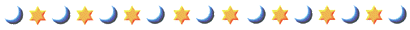
1ヶ月ぐらいしただろうか、カタカタと木箱が震えていた。
僕は気味悪く思ったが、そのまま観察してみた。
すると、木箱が内側から押し開けられ、中から奇妙な生物が出てきた。
ぬいぐるみの、2足歩行の猫を、そのまま小さくしたような、本当に奇妙な生物だった。
にゃかにゃかとしか鳴かないので、僕も『にゃか』とそいつを呼ぶことにした。
にゃかに何を食べさせたら良いかと迷ったが、意外とコイツは何でもイケるようで、虫とかは食べることはしないが、人間と同じものなら、食べた。
僕とにゃかとの生活が始まった。
僕はいつもの日常のつまらない出来事をにゃかに話す。
にゃかは分かっているのかいないのか「にゃかにゃか」と僕の話を聞いている。話を聞いてくれる誰かがいることは、存外、僕の人生にメリハリを与えた。
そんな生活が1年も続いただろうか、突然、にゃかが倒れ、動かなくなった。
心配してゆさゆさとその小さな体を揺り動かしてみると、にゃかはむっくりと起きあがった。
「あぁ、この幸福をなんて言い表したらよいでしょう」
にゃかは突然、人間の言葉を使ってしゃべりだした。
「あなたに拾われてから丁度1年。とうとうこの日がきました。ありがとう。なんとお礼を言って良いのやら」
にゃかは「にゃかにゃか」と鳴いていた時と全く同じ声で話しだした。
――つまり、悪い魔法使い(うさんくさい話だ)に姿を変えられてしまい、元に戻るためにはある人間の元で1年間過ごさねばならなかったということらしい。
「是非ともあなたにお礼をしたいのですが、どうしましょうか」
あまりにも嬉しそうに、幸せそうにそう言ってくるので、僕もなんだか嬉しくなってしまった。うさんくさい身の上話は身の上話として。
「そんなに嬉しそうな顔をしているなら、君のその幸せを僕に分けてくれたらいいのさ」
特に深い意味はなかった。なんとなく、口をついて出た。ちょっと歯の浮くセリフ。
そうすると、にゃかは満面の笑みを浮かべた。
「ありがとう、そう言ってくれるととても嬉しい」
にゃかは僕の指に抱きついた。
気づけば、僕はにゃかになって、僕の指を抱きしめていた。
「そう言ってくれて本当に嬉しい」
目の前の『僕』はそう言って僕の顔を覗き込んだ。
『僕』は僕をつまみあげると、どこから取りだしたのかあの木箱を僕に見せた。
「そのお礼に、1つだけ魔法を教えてあげる。私もこう教わったの」
『僕』は僕に1年間人間の元で過ごし、その人間と成り変わる魔法を教えた。
「いい人間に出会えると良いね。私、いや、僕はちょっとツラかったんだよ。最初の1ヶ月は炎天下にさらされて箱の中は蒸し風呂状態だったからね。いっそのこと死ねるかと思ったのに、その『にゃか』の体じゃ死ぬに死ねない」
『僕』は木箱に僕を押しこんだ。
「じゃぁ、うまくやりなよ」
『僕』は僕の口調で僕の入った木箱をどこかへ置き去りにした。
にゃかにゃかと鳴いていたアレはどうやら演技だったらしい。
なるほど、確かに人間語を解さない方が相手も油断をするだろう。
はて、僕はなんと鳴いてみようか。「ぬーぬー」「ぐわぐわ」「ぴよ」どれもしっくりこない。
とりあえず、誰かが木箱を拾うまでは、考えてみよう。