5.生娘は不慣れに震える
運ばれてきた夕食をきれいに食べ終えたユーディリアは、今日はもう寝るからとマギーを下がらせた。
マギーもユーディリアから得た情報で、色々と独自に動いているらしく、親衛隊の副隊長と話をすることができたと報告してくれた。
(まぁ、この状況をそう簡単に覆せるとは思わないけど)
薄い寝間着に着替えたユーディリアは、寝台へは向かわずに、カウチへと腰を落ち着けた。
疲れていないわけではない。馬車で移動すること二日、揺られ続けた身体はギシギシと悲鳴を上げてるし、今日だけでも緊張を強いられるできごとが三回はあった。
今後のことを考えると、正直心が重い。
だが、このまま、ミレイス、セクリア、レ・セゾンの三国の行動に流されるのを待つしかないと諦めはついていた。
―――諦められないのは、自分の中にくすぶっている怒りの感情だ。何らかの形で、お返しをしないことには気が済まない。
室内を軽く見回す。将軍もベリンダもリッキーも姿が見えない。こんな時、自由の身の彼らがうらやましい。
上体を倒し、カウチに寝そべる。
悲運の王女ぶりっこは、まだ続けるべきだろうか。
いつまでリカッロ王子に彼らのことを隠し通せるだろうか。
この先、ミレイスとセクリアのどちらの味方として立つべきか。
考えるべきことはたくさんあった。
とりあえず目を閉じて、今日あったことを反芻する。
「―――おい」
声をかけられた。声は男のものだったが、将軍のものにしては声がはっきりしている。
「そんなとこで寝てんな。脅かしがいがねぇだろうが」
乱暴な物言いに目を開けると、目の前に真っ黒な瞳があった。
いつの間にか寝てしまったのか、ユーディリアはぼんやりとしたまま、ゆっくりと上半身を起こす。
色々と考えていたはずだが、いつの間にか寝てしまっていたようだ。
無理もない。今日は本当に疲れていたから。
首が少し痛いのは、無理な体勢で寝ていたからだろうか。
(えぇと?)
とりあえず、現状把握するために、頭のゼンマイをキコキコと巻く。
(えぇと、今どういう状況なんだっけ?)
―――答え。部屋のカウチでうたたねしてたら、リカッロ王子に起こされたところ。
「えぇと、リカッロ殿下?」
「なんだ?」
「どうして、あなたがここにいらっしゃるんでしょうか……?」
「オレはここに寝に来ただけだ。隣に潜り込んで驚かそうと思ったが、残念な結果になったがな。……おい、お前、ちゃんと起きてんのか?」
「一応、起きています」
起きていると主張する割には、そのまぶたが落ちかけている。リカッロは呆れた表情を浮かべて、明らかに寝ぼけているユーディリアの頬をうにっとつまんだ。昼間と違い、振り払われることもなかったので、そのまま、むにむにと感触を楽しむ。
「えぇと……、ここで寝るとおっしゃいました?」
「あぁ。予定通りだろ? お前はこの国に嫁ぎ、結婚相手と夜を共にする、と」
「……」
リカッロの言葉が頭に入っているのかいないのか、ユーディリアはぼーっとしながら、頬をむにむにとつままれている。
「楽しいですか、それ?」
「あぁ、感触が気持ちいい」
どうやら覚醒してきたようだと判断し、リカッロはようやく手を放した。
「何か言いたいことはあるか?」
「いいえ、特に何も。……寝るのでしょう?」
立ち上がって寝台へと向かうユーディリアの背に、「また人形みてぇなつまんない顔に戻りやがって」とリカッロは舌打ちした。
カウチの脇のテーブルからランプを取ると、彼女の後を追いながら部屋のあちこちにある燭台の火を消していった。そして寝台へ向かう途中、ドアの脇に立てかけていたサーベルを、寝台の隣へと移動させる。
ユーディリアは躊躇なく寝台へ身をすべり込ませた。少なくともリカッロの目にはそう映った。
「動揺しやしねぇ」
毒づいた彼も、ナイトテーブルにランプを置くと、その反対側から寝台へ上がる。
「あなたの言うように『予定通り』ですから。それに、こんな時にそういうことをするとも思えません」
薄暗い部屋の中、仰向けで寝ているユーディリアは、まっすぐ天井を見つめて、そんなことを言う。
「さぁ、どうかな?」
「……サーベルを枕元に置くほど警戒しているのに、わざわざ無防備な姿を晒すんですか?」
その言葉に、ちらりと寝台に立てかけたサーベルを見たリカッロが小さく舌打ちをする。
「お前、ムダに頭が回るな。取るに足らない国の何もできねぇお姫様だと思ってたのによ」
「外に嫁ぐと決まった時から、色々と気構えを教え込まれました。それに、本当に頭の回る人であれば、『何もできねぇお姫様』を演じていますわ」
「お前は演じないのか?」
「最初に御者と侍女と箱馬車を守ると決めた時に、その道は諦めています」
いまさら取り繕っても無駄でしょう?と彼女は呟いた。
「なるほど、で、お前はオレがほんとに何もしねぇと思ってるんだな?」
その言葉に、ユーディリアが不穏な気配を感じた瞬間、布団の中で腰をさらわれ、抱き寄せられた。服越しに感じる体温が、冷え切った彼女の背中を温める。
「どうした、震えてるぞ?」
当たり前だ。最初こそ寝ぼけていたものの、覚醒してからはずっと、将軍の書いた台本通りに口を動かしていたのだ。今日初めて会った人間と床を共にするなんて、動揺しないわけがない。
「まだ城内が収まりきっていない状況で、することですか?」
「コトに及ばなくても、こうやって遊ぶことはできる」
耳元で囁かれ、意図せずに体が震えた。
「そういう人間らしい表情してりゃいいんだよ。国のためとか言って人形の顔してる時より、百倍いい顔だぜ?」
そう言えば、人形みたいとかつまらないとか散々言われていた気がする。
―――が、そんなことはどうでもよかった。とりあえず、この何されるか分からない状況から、どうにか脱出したかった。
人間らしい顔を見せろと言うのなら、多少は感情を露わにすれば、解放されるだろうか。
『―――』
面白そうに様子を眺めていた将軍が、何事かを告げた。その言葉が全くその通りだと思ったので、ユーディリアはまるで伝言ゲームのように口を開く。
「この国の残党に警戒するのはいいのですが、寝ている間にわたしに刺されるとは考えないのでしょうか?」
声を出したことで、少しだけ、心が落ち着きを取り戻す。
「お前は刺さない」
きっぱりと否定され、ユーディリアは驚いて目を丸くした。
「お前はセクリアを自国として認識していないだろう。生まれ育ったレ・セゾンを第一に考えている。レ・セゾンの判断をお前は待つしかない」
淡々と理由を説明され、ユーディリア自身も確かにそうかも、と納得してしまった。それと同時に、そんな解析ができるほど、自分のことを観察されていると分かって、かぁっと身体が熱くなった。
「それに―――」
背中から抱きしめていた手を動かし、リカッロの手が何かを探すようにユーディリアのあちこちに触れた。そして、胸の前で祈るように握られていた手を見つけると、その無骨な手で遠慮なく手のひらを撫でる。
節のある無骨な手の感触に、ユーディリアは力を入れることも忘れて、ただ予想外の行動に怯えていた。
「手にマメひとつないのに、お前が武器を扱うのか?」
その言葉に、視界の外へ行ってしまった将軍を思い出す。ユーディリア自身、剣も弓もからっきしだが、将軍に身体を貸せば、その腕前は半端ない。とはいえ、元々鍛えていない身体を酷使するわけだから、後日の筋肉痛も半端ないのだ。過去に何度か将軍の力を借りたが、その度に、もうやるものか、と思ったものだった。
「そうですね。わたしが扱える刃物は包丁ぐらいでしょう」
「料理ができるとでも言うのか? 一国の王女が」
「それはもう、色々切り詰めても貧乏な国ですから。賓客をおもてなしするような時を除いて、当番制でしたわ」
その言葉に、リカッロが小刻みに体を震わせるのを感じた。
「笑っても構いませんわよ」
その言葉に、リカッロは抱きしめていたユーディリアを解放し、ごろりと背中を向けると、遠慮なく声を上げて笑い出した。
「……くっ、久々に笑わせてくれるじゃねぇか。神秘の国とはよく言ったもんだ」
「そこまで笑えることとは思いませんでした。―――お休みなさい」
バカにされてムッとしたのもあったが、この疲れる会話をとっとと終わりにしたくて、最後に就寝の挨拶を付け加えた。
「あぁ、ゆっくり休みな」
向こうもこれ以上、こちらに構って来る気はないのだろう。ユーディリアは少しだけホッとして目を閉じた。
うたたねしたとは言え、未だ身体に疲れが残っている。
だが、こんな状況では、いつ眠りに落ちることができるかも分からなかった。
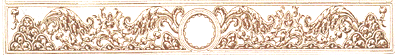
(案外、わたしって図太いのかもしれない)
そう自覚したのは、ちょうど、寝間着から藍色のドレスに着替え終えた時だった。
朝、隣で寝ていたリカッロ王子がごそごそと起きる気配に、目が覚めて、上半身を起こした。やはり疲れがあったのだろう、あれから何刻も経たないうちに眠ってしまったようだ。
「なんだ、起きちまったか。……いや、まだ起きてねぇな」
そんなことを言われた気がする。
「お前の侍女と御者を見送りたければ、早めに目を覚ましておくんだな」
部屋を出て行く時の彼の言葉に、ようやく頭が起きなければと身体の各所に指令を出した。
(……というか、部屋を出て行く時、寝間着じゃなかったわよね?)
たぶん、室内で着替えていたのだろうが、そんな記憶はなかった。上半身を起こしたままで二度寝していたのだろう。自国にいる頃からよくあることだった。
寝台から出て、将軍やリッキー、ベリンダに急かされてクローゼットを開け、ベリンダの指した藍色のドレスを手にとって、もそもそと着替えたユーディリアは、ようやく本当に覚醒してきたのである。
鏡台へ座ると、もさっと膨らんだ金の髪に櫛を入れ、自国にいた時と同じように、慣れた手つきで太い三つ編みを作っていく。寝癖を隠すにはちょうど良い髪形だ。
「さぁ、急ぎましょう」
ぺたんこの靴を履いたユーディリアは、まだ覚醒しきっていない足に、とっとと起きて、と指令を出す。
階段で足がもつれて転びそうになったことを除けば、概ね無事に城門へと着いた。昨日の午後、ちょうど、ドニーやブリギッテと別れた場所だ。予想通り、見慣れた箱馬車の姿がある。
「なんだ、間に合ったのか」
使者となる部下と何事か話していたリカッロ王子が、意外そうな目を向ける。
「姫様!」
馬車に乗ろうとしていたブリギッテが、顔をくしゃりと歪めた。
「ブリギッテ! ドニー!」
「嫁ぎ先では、その髪はおやめくださいと、王妃様も申しておりましたのに」
「ごめんなさい、ブリギッテ。急いでいたから、つい、いつものクセが出てしまったの」
「侍女をつけていただいているのでしょう? 姫様、きちんと結い直していただくんですよ」
「もう、ブリギッテったら、こんな時にお小言? お父様によろしくね。別に危険な目には遭ってないって。お母様やお姉様、妹達も、どうか安心させてちょうだい」
気遣うような言葉に、侍女の涙腺が緩む。
「まぁ、ブリギッテったら。あなたのことも心配よ。だって、また馬車の旅なんですもの。……ドニー、この馬車のことはあなたが一番良く知っているわ。どうか、安全で、できるだけ快適な速さでお願いね」
「姫様。……ご安心を。わっしは、もう十年もこの馬車と付き合っております」
ブリギッテの涙が感染したのか、ドニーも目を潤ませる。
「あなたのかわいい息子さんたちによろしくね」
ユーディリアの言葉に、ドニーはその帽子を胸のあたりでぎゅっと握りしめ、何度も頷いた。
「そろそろいーか?」
最後の打ち合わせが終わったのだろう。リカッロは別れを惜しむ主従に無慈悲な言葉を投げつけた。
「えぇ、構いませんわ。……それではドニー、ブリギッテ、お父様によろしくね」
「姫様のほうこそ、くれぐれもお気を付けください」
ブリギッテは念を押すように涙声を絞り出すと、深々と頭を下げて馬車へと乗り込んだ。ドニーも御者席へと足を向ける。
その隣で、使者は自分の馬にまたがり、リカッロに対して頭を軽く下げた。
そうして、騎馬と馬車がお互い歩幅を合わせるように歩き出すと、その後ろに三、四騎の騎馬が続いていった。彼らも護衛役としてレ・セゾンに行くのだろう。
「……使者様も馬で行かれるのですね」
小さくなっていくその姿を見送りながら、ユーディリアがぽつり、と呟いた。
「問題か?」
「いいえ、懸命なご判断だと思っただけですわ」
初めて乗る人間が二日も揺られるには、あの馬車は拷問過ぎる。
ユーディリアは隣のリカッロに体を向けた。気圧されないように、拳を強く握る。
「リカッロ殿下。差し支えなければ、今日は書斎で過ごしたいのですが、よろしいでしょうか?」
「書斎? そんなもんあったか?」
「居室と同じ三階に、主に王族の使用するプライベートなものがあります。……でしゃばるな、と言われたわたしには、することがありませんの」
最後の言葉だけを、そこはかとなくこちらを気にしている彼の部下や、セクリアの使用人には聞こえないよう、声を低くする。
「まぁ、いいだろう。未来の妻の願いぐらい、寛容に聞いてやるさ」
「ありがとうございます」
「つまんねぇ仏頂面しやがって、少しは愛想笑いでも浮かべたらどうだ?」
「まぁ、それは難しい相談ですわ」
セクリアの人間がいる前で媚びてみせろと言われて、はいわかりました、というほどユーディリアも落ちぶれてはいない。
リカッロに軽く頭を下げると、彼女はくるりと背中を見せてしずしずと歩き出した。
「どうも、一筋縄じゃいかねぇオンナだな」
「リカッロ様、そのぐらいにしといてください。視線が痛いですよ」
「はんっ、視線に刺されたぐらいで、死にゃしねぇよ」
心配性な副官に軽く手を振り、彼も仕事に戻るべく、彼女を追うように城の中へと歩き出した。