15.異能者は不本意に涙する
―――ユーディリアはじんじんと響くその部分の痛みに耐え兼ね、眉根にしわを寄せた。「何だ? あれだけ丁寧にしてやったのに不満か?」
仰向けに寝ていたユーディリアを覗きこむような、リカッロのおどけた顔が視界に入る。
「……女性経験が豊富そうなあなたに『疲れた』と言わしめるほど丁寧だったとは理解していますが、―――正直、そういう問題でもありません」
「ちぇっ、最後の方は、あれだけいい声で鳴いてたから、もう大丈夫だと思ったんだけどな。やっぱ処女は難しいわ」
オブラートに包む気遣いもないセリフに、ユーディリアは一発ぐらい殴っても問題ないはずだ、と拳を振り上げる。
「まぁまぁ、落ち着け落ち着け」
あっさりと防がれただけでなく、上半身を起こしていたリカッロは、捕えた拳に軽く口づけをしてきた。ユーディリアは慌てて自分の手を引っ込める。この話の流れをどうにか逸らせようと考え、彼女は別の話題を持ち出すことにした。
「ずいぶんと、傷があるんですね」
鍛え抜かれた上半身はその裸身を惜しげもなく晒し、ランプに照らされた背中や脇腹には薄く傷跡がいくつも見えた。
「あぁ、戦場に出ていれば、いやでもな。……なんだ、お前もひっかき傷でも残したかったのか?」
「言われてみれば、思いっきり引っ掻いてやればよかったんですのね」
ひっかき傷を額面通りに捉えたユーディリアに、リカッロは思わず吹き出した。
「……いや、すまん。何でもねぇ」
「お望みでしたら、今からでも引っ掻いてさしあげましょうか?」
バカにされたと思ったユーディリアは、布団で胸から下を隠しながら、上半身を起こした。
「そんなにやりてぇなら、別にやってもいいが、……こっちも仕返しするぜ?」
まるでいたずらを思いついたガキ大将のような表情に、ユーディリアはうっ、と怯んだ。その様子に満足げに笑ったリカッロだったが、何かを思いついてひどくまじめな表情をする。
「……ここには、オレとお前しかいない。レ・セゾンの王女としてじゃなく、ユーディリア個人の意見を聞きたい」
いきなりの申し出に困惑するユーディリアを見て、その黒い瞳が柔らかい光を帯びた。目の前の彼女の感情を取りこぼさないようにと、右手がユーディリアの首筋に伸びる。
「また、そのずるい手を使うんですの?」
「こうしないと、お前は嘘をつくからな」
何度触れられても動悸が激しくなるのは、頸動脈が人体の急所だからだとユーディリアは思う。
「……聞きたいことというのは?」
やや警戒して聞き返した彼女に、リカッロは珍しくその質問をするのに躊躇を見せた。
「リカッロ殿下……?」
名前を呼ばれ、リカッロは数拍、目をつぶった。
「お前は、オレを憎んでいるか?」
予想もしていないその問いかけに、ユーディリアはこぼれんばかりに目を見開いた。リカッロの質問の意図がくみ取れない。話の流れから言えば、さきほどの行為について、良心の呵責があるとも解釈できるが、そんな殊勝な人間ではないと思う。
しばらく悩み、ユーディリアは思ったままを口にすることにした。
「別に、憎む理由もありませんし、……意地悪な方だなぁ、と思ってはおりますけど」
「……そうか」
「どうして、そんなことを聞くんですの?」
「手合せした時に、剣筋に容赦や遠慮が全くなかったからな。この機会に殺そうとしているのかと思ったぜ」
「それは……、その、申し訳ありません。一度始めてしまうと、つい、夢中になってしまいますので」
脈が乱れたことに、リカッロの目がすい、と細められる。ユーディリアは慌てて言葉を重ねた。この話題はまずい。
「で、でも、どうしてそんなことが気になったんですの?」
「お前は、娶る相手から殺意を感じて放っておけるか?」
リカッロの問いに、ユーディリアは僅かに首を傾げた。
「……結婚は、国と国との契約でしょう? そこに私情を挟むんですの?」
脈が乱れないことに、リカッロはがっくりと肩を落とし、そして唐突に笑い出した。
「リカッロ殿下……?」
「はははははっ……。あぁ、すまねぇな。全く、お前はたいしたお姫様だよ」
リカッロは困惑するユーディリアを軽く引き寄せた。突然のことに、ユーディリアは引かれるままに隣に座るリカッロの腕の中に捕えられる。無防備な背中に手を回され、おおげさに体を震わせた。
「オレみたいな男には、お前ぐらいの訳分かんねぇじゃじゃ馬が丁度いいのかもな」
自分に言い聞かせるように呟くと、体勢を保つために自分の胸に添えられていたユーディリアの手を取った。治りかけてはいるものの、まだ痛々しいその手のひらにそっと口づける。
「痛いか? ……すまなかった」
妙に素直な謝罪と、手に口づけるという気障な行為に、ユーディリアは頬を赤らめた。
「―――手合せのとき、リカッロ殿下に、お怪我はありませんでしたの?」
「あぁ、オレは大丈夫だ。……あぁ、そうだ。一応聞いておきたいんだが」
「なんでしょう?」
「他にお前が我を忘れるほど夢中になることはあるか?」
ぴくり、と身体に力を入れてしまったユーディリアに、リカッロは小さく低い声で「おい」と促した。
ユーディリアは将軍、ベリンダ、リッキーの三人の顔を脳裏に描くと、観念したように長く息を吐いた。
「歌と、読書です。歌い続けて喉を嗄らしたこともありましたし、城の書庫にこもって飲まず食わずで過ごして倒れたこともありますわ」
「……なるほど。それならこっちでも気をつけておこう」
そのまま、ユーディリアはリカッロの身体に寄りかかったまま、しばらく無言で空を見つめた。
「あの――」
「なんだ?」
「わたしからも、質問してもよろしいですか?」
「……なんだ?」
ユーディリアは身体をひねり、自分の方から触れることに震えそうになる指を、そっとリカッロの首筋に添えた。その深海の色をした視線が、感情の揺らぎをも見逃さないように、まっすぐにリカッロに注がれる。
「これは仕返しか?」
面白がるように見つめ返すリカッロに、ユーディリアは肯定も否定もしなかった。
これを直接聞かない方がいいのかもしれない。ハルベルトのことを思い出し、ユーディリアはきゅっと下唇を噛んだ。だが、それでも何とか声を絞り出す。
「……あなたも、わたしのことをバケモノと思っていますの?」
真剣そのもので返事を待つユーディリアを、リカッロは鼻で笑った。
「お前は単なるじゃじゃ馬だ。バケモノだなんて思ってるのは、あのヘボ王子ぐらいだろ」
その答えに、ユーディリアは笑うのに失敗して、変な顔になった。そして、その瞳から涙がぽろり、とあふれ出る。
「おい……?」
「あ、申し訳ありません。これは、そのびっくりした拍子に、と言いますか―――」
明らかな嘘をつくユーディリアが、「もう休みます」と腕の中から逃れようとするのを、リカッロは引き止めた。
「平気なフリなんてすんな。今ならオレしか見てねぇ」
その顔を胸に押し付けるように抱きしめられたユーディリアは、小さく嗚咽を洩らした。
「まったく、あれだけの復讐をするほどに怒っておきながら、自分が傷ついてないとでも思ってたのか?」
―――その通りだ。自分では傷ついていないと思っていた。
自国にいる頃から、異能持ちの王族というだけで、一歩引かれていたのだ。いまさら、婚約者から罵倒されたぐらいで、と思っていた。
長年、婚約者として付き合っていた人にまでそう思われていたと知っても、大したことはないのだと言い聞かせてきた。
冷たく凍らせた感情が、涙とともに溶けていくのを感じながら、ユーディリアは肩を震わせた。
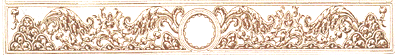
一か月後、ようやくセクリアがミレイスの属国として周辺国から黙認されつつある頃、リカッロとユーディリアは、レ・セゾンとの国境に来ていた。
晴天に恵まれた中、急ごしらえの天幕の中で、リカッロとレ・セゾン国王がそれぞれ友好条約に調印をする。その条文の中には、ユーディリアの扱いについても記載されていた。
調印式の後、ユーディリアはリカッロに伴われて、父親の前に姿を見せた。
「私のかわいいユーリ。元気そうで何よりだ」
「お父様……!」
調印式という場にふさわしく、鈍色の質素なドレスに身を包んだユーディリアは、きれいに結い上げた髪が乱れるのも構わず、父親に駆け寄った。
首に手を回して抱き着くと、いやに冷静な声がユーディリアの頭に響く。
『リカッロ王子とはうまくやっているようだな』
『はい、お父様』
神秘の国レ・セゾンの当代国王は、触れている相手と心話ができる力の持ち主だ。
『ずいぶんと派手なことをやったようだが、お前の力はバレていないだろうね?』
『……分かりません。気付いているのかいないのか、追及されてはおりませんけど』
国王は娘の肩を掴むと、抱きついて来た娘の体を離し、その顔を覗き込んだ。
「リカッロ王子は若いが優秀な人物のようだ。ハルベルト王子よりずっと頼りになるよ」
「まぁ、お父様ったら、褒めても何も出ませんわ?」
表面上は、親子の触れ合いを楽しむ父と娘だが、密談は続く。
『まぁ、そろそろ周辺諸国に我々の力を思い出させても良い頃だ。もし、バレたなら、所定の手続きで知らせるように』
『……あの青い花が懐かしい、ですわね』
陰りない笑顔を浮かべるユーディリアだが、暗号を思い返した時に、少しだけ瞳が曇った。本当に無能だったら、こんな暗号なんて必要なかったのに、と。
『お前は無能ではないよ』
『お父様?』
『お前の力は外向きだ。だからこそ元老院も無能と判断した』
予想もしなかった言葉に、ユーディリアは声を失った。
『グレイスが心配していたぞ。お前が自分が無能であることを気にしている気がする、とな。……あの娘の能力は不安定だが、どうやら的中していたようだな』
末の妹は血縁や親しい相手の心を視ることができる。だが、時間・相手・距離ともに不安定で、元老院も能力の判定に苦慮していると聞いた。
『お前の三人の相談相手によろしくな』
にっこりと嘘のない笑みを浮かべた父親は、娘に触れていた手を離した。
「たまには手紙を書きなさい。お前の母親も心配していた」
「えぇ、お父様。リカッロ様に頼んでみますわ」
軽く手を挙げて背を向けた父親に手を振り、ユーディリアもまた背を向けた。
「もう、いいのか?」
「えぇ、……何か?」
こういうニヤニヤした表情の時は、何かある、と身構える。
「ずいぶん親と仲がいいんだな」
そういえば、ミレイス王族の中ではひどい扱いを受けていたんだっけ、と庶子出身の王子を前に、ユーディリアは無神経なことをしてしまったかと反省する。
「お前……」
不用意な言葉を避けようと、ユーディリアは続く言葉を待つ。
「寝起きの悪さは母親譲りなんだってな」
「っ! まさか、それ、調印式の時に―――」
「国王陛下じきじきの言葉だぜ? いや、ありがたいなぁ……」
からかうように口の端を持ち上げるリカッロに、こぶしを振り上げかけたユーディリアは、慌てて自分を押さえた。ミレイス、レ・セゾン両国の人間が揃っている前で、はしたない姿を晒すわけにはいかない。
二人のじゃれ合うようなやり取りを知っているミレイスの兵が忍び笑いを洩らしていた。