1.寝耳に水
「申し訳ありませんが、おっしゃっている意味がよく分からないのですが……?」セクリア王城の一室、若き王と王妃の寝室からその声が響いた。
セクリアが大国ミレイスの属国となって一年、ようやく正式に王となり王妃となった二人のじゃれ合いは、この城で立ち働く人間にとっては、常と変わらない。
「何度聞いても同じだ。お前が自身の護衛を不要と言うなら、その技量を示せばいい」
いつもながら一方的なその言葉に、ユーディリアは手に持っていた刺繍の木枠をテーブルに置いた。このまま掴んでいたら、思わずぽっきりやってしまうかもしれない。
ちらり、と目の前に仁王立ちになっている夫・リカッロの顔を見れば、意地悪い笑みを浮かべていた。非常に腹立たしい。
「……どうして、そのような話になったのか、順を追って説明していただけますかしら?」
いいだろう、とリカッロは鷹揚に頷いた。
―――事の起こりは、貴族上がりの新兵の発言だった。
「一国の王妃が護衛もつけずにぶらぶら歩いて、何かあったらどうするんですか」
セクリアがミレイスの属国となって一年、その頃から親衛隊にいた人間ならともかく、そうでない人間にとっては、王妃が剣をぶん回すなど、眉唾ものの噂でしかない。
事実、ユーディリアはあれ以来、人前で剣を振るうことはしていなかった。
国民のユーディリアに対する印象と言えば、隣国から嫁いで来たのに、政変に巻き込まれたかわいそうな王妃、といった所だ。一時期こそ、裏切り者とも言われていたが、救貧院への訪問など、国民に姿を示すようになると、その声も次第におさまっていった。
知識も広く、慈愛の心を持つ、しとやかな王妃。それが国内に広まった彼女の印象である。
「……ということで、まぁ、面倒だから見せつけてやれ」
リカッロの言葉に、ぴくり、とユーディリアの頬がひきつる。彼女の視界には、自慢のヒゲを撫でながら「腕がなるのぅ」と呟く甲冑姿の老人が映っている。半分透けているが。
「それとも、なんだ? 将軍はイヤがってるか?」
「……」
むしろノリノリだった。だが、それを口にしたら負けてしまう。
「近頃、体調が優れませんので、辞退させていただきます」
「あぁ、頭痛に吐き気だったか? それにしちゃ、顔色はそんなに悪くなさそうだが。……刺繍も進んでいるようだしな」
木枠には、小さな鳥の刺繍が刺しかけてある。
「まぁ、それなら余計に護衛が必要だな。さっそく人選を……」
「ま、待ってください」
慌てて立ち上がったユーディリアは、去ろうとするリカッロの服の裾を掴む。
「なんだ? ――おい」
ニヤリと笑ったリカッロだったが、彼女がくらり、と立ちくらみを起こしてよろけるのを、慌てて支えた。
「すみません、少し、集中し過ぎてしまったみたいですわ」
言われてリカッロがテーブルに目をやると、縁に刺繍のほどこされた大きい布が一枚畳まれている。こちらはどうやら完成品らしい。
「いったい、何枚やる気だ? ……いや、違う。それらをどうする気だ?」
目眩のおさまったユーディリアは、その深海の瞳で夫の黒炭の瞳をまっすぐに見据えた。
「リカッロには関係のないことですわ」
「まぁいい。どちらにしても、ユーリ、お前の選択肢は二つしかない。ぎゃあぎゃあ騒ぐ新兵二人を叩きのめすか、大人しく護衛をつけるか」
「新兵が相手、ですの?」
隣で夫婦の会話をじっと聞いていた黒髪の歌姫ベリンダが、若い子が二人もいるの?と目を輝かせた。
その一方で、甲冑姿の将軍が肩を落とし、新兵が相手か、と落胆する。
『ねぇねぇユーリ。新兵って二人だけじゃなくて、たくさんいるんでしょ? だったら、見たい見たーい』
ベリンダの脳天気な声に、ユーリは大きくため息をついた。
「お前の相談役は何と言っている?」
「ベリンダは、新兵の品定めがしたい、と。将軍は新兵が相手と聞いて肩を落としてます。リッキーは―――」
『じ、自分は反対です。体調が悪いのに、そんな激しい運動なんてもっての他です』
珍しい、とユーリは目を丸くした。いつもは周囲に流されることの多い彼が、こんなにはっきり拒絶を示すのは珍しい。
「リッキーは?」
リカッロに名指しされ、彼から姿が見えていないにも関わらず、びくり、と体を振るわせたメガネの青年がリッキーだ。
「リッキーは反対しています。体調がよくないのに、って」
自分が若くして亡くなったから、そういうことに慎重になっているのかな、とユーディリアは心の中で推測する。
『やだ、リッキー。ちょっと気にし過ぎよ? いくら……だからって、大丈夫だって。それに新兵相手なら、将軍だって五秒とかからずに終わらせるでしょ?』
『確かに、歌姫殿の言うとおりじゃ。なんなら二人まとめて相手にしてやるわい』
「ちょ、ちょっと待ってよ。どうしてそういう話になるのよ」
突然、慌てた声を上げたユーディリアに、どうやら面白い展開になっているらしい、とリカッロは静観する。彼女の三人の相談役の存在を明かされて以来、こういったことは度々あった。もはや萱の外にされるのも慣れてきている。
『でも、万が一ということもあります。それなら自分は大事をとった方がいいと思うんです。多少、窮屈な状態になっても』
『アタシはイヤよ? せっかく誰の目も届かない所で伸び伸びしてるのに、今更?』
『まぁ、それなら、こちらは必要最小限の動きで沈めてやるいわい。それならどうじゃ?』
『必要最小限?』
『その新兵の技量が、どれほどのものか分かるかのぉ?』
自分を置いてきぼりにして進む会話の中、いきなり話を振られたユーディリアは、リカッロを見上げた。
「その新兵二人の剣の技量はどれくらいですの?」
「ん? あぁ、ザッカードと同じかちょい上ってとこだな」
『それならば問題ないじゃろう。何なら、ドレス姿のままでやって良いぞ』
『そうね! それなら、相手だって自分より上だって認めるわ!』
『……でも』
それでも渋るリッキーは、よほどに気がかりなことがあるのか、ちらり、とユーディリアを見た。
『そうじゃのぅ。……そうじゃ! この間、見たがっていた返し技を披露しよう。それでどうじゃ?』
『う、……うん! それなら、いいですよ。確実に最小限の運動で済むし』
リッキーの中で「心配」に傾いていたはずの天秤が、一気に「好奇心」に振られたのを目の当たりにして、ユーリは大きくため息をついた。
この三人の意見が一致してしまえば、ユーリ一人に勝ち目はない。
「結論は出たか?」
「……えぇ。でも、一つだけ、条件をつけてもよろしいかしら?」
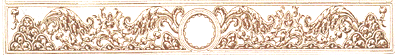
親衛隊の鍛錬場には、普段よりもずっと多い兵が詰めかけていた。
「どうぞ、遠慮は無用ですわ」
中央でにっこりと微笑む王妃。その姿は、普段、むさ苦しい男達が汗を流す場には、似つかわしくない。
右手に木刀を持っている彼女は、一年前にここでリカッロと手合わせをした時とは違い、普段着のままだった。
モスグリーンのドレスが鍛錬場では浮いて見える。
その丈こそ足首が見えるほどの長さだが、そこから覗く足には握り拳ほどの高さのヒールの靴を履いており、動きにくさを強調する。
彼女と対峙する新兵は二人。彼らがチラリと王を見遣れば、遠慮はない、とばかりに頷かれた。
「いやぁぁぁっ!」
気合いの声を上げ、一人が打ちかかる。
すっ、と目を細めた王妃は、木刀を打ち合わせると―――
「っ?」
まるで、打ちかかってきた木刀を巻きとるかのように、くるりと回し、新兵その1の足を軽く払った。
新兵その1は、くるりと体を回転させられ、背中から倒れる。
「ふっ!」
強打した背中が吸気を拒み、口元から甲高い音が漏れた。
「くっ!」
新兵その2が、そこを突いて挑みかかる。
すると、何を思ったか、王妃は倒れた新兵その1に、自分の木刀を渡すように放った。
「!」
まさか武器を持たない相手(しかも王妃)に挑むのは、と躊躇するが、勢いよく蹴りだした足は止まらない。
(えぇい!)
ここまで来たからには、と新兵その2は、木刀を繰り出す。一瞬、相手の口元に笑みがこぼれたように見えてぞっとした。
「剣筋が素直すぎる」
いつもの慈愛に溢れた声ではなく、それはまるで、上官のような冷たい指摘。
そう思った瞬間、新兵その2も宙を舞った。
どさっ、と彼が倒れる音とともに、息を詰めて見守っていた親衛隊の間から、ため息が漏れた。
「このような礼を欠いた格好で、申し訳ありませんでした」
王妃ユーディリアは軽くドレスの裾を摘むと、誰にともなく頭を下げる。
そして、倒れた二人に優雅に笑いかけると、そのまま鍛錬場を後にした。
「さて、これで分かったな? 少なくともお前らヒヨッ子の護衛は必要ない。せいぜい励め」
見物していた王は、その場を副官に任せると、王妃の後を追うように出て行った。
―――いや、実際、追いかけるつもりだった。
(まぁ、派手にやってくれたもんだ)
動きにくいドレス姿、しかも一人は武器を持たずにあしらったことで、少なくとも護衛が必要だと言う理由を鮮やかに失わせて見せた。
「将軍も大したもんだ」
一人目のあしらい方は、リカッロ自身も同じことができると確信できる。
だが、二人目のアレは、かなり難しい。
新兵のまっすぐ過ぎる打ち込みも問題だが、体をひねって避けた後、相手の手首に手を添えて、おそらくその手をひっくり返しただけだ。相手の力を利用し、手首を返すだけで、体全体をもひっくり返す。それを将軍は、ユーディリアという弱い身体を使ってやってのけたのだ。
「やっぱ、個人的に教授願いたいな」
逃げるように鍛錬場を出て行った妻の姿を探し、首をめぐらせれば、中庭の方へ歩いて行くグリーンのドレスが目に入った。
「おい、ちょっと待てよ」
制止の声も聞かず、中庭に出たユーディリアは、すぐ近くにあったベンチに腰掛けた。そして、両手で口元を押さえ、うつむく。
「なんだ? 別に自己嫌悪に陥るようなことでもねぇだろ?」
「将軍、……ちょっと、やり過ぎです」
夫の言葉を無視し、ユーディリアはリカッロに見えない相手に話しかける。
「いくらリッキーのリクエストに答えるからって、……うぅ、せっかく一年かけて、あのイメージを埋もれさせたのに」
少し長くなりそうだ、と思ったリカッロは、ユーディリアの隣に腰掛けた。
「それは、確かに、護衛がいると不都合もありますけど、それでも―――。あ、リカッロ、何かご用ですか?」
将軍から促されたのか、話を切り上げたユーディリアに、リカッロは追いかけて来た理由を素直に告げた。
「いや、二人目をあしらった手口を、将軍の口から解説して欲しいと思っただけだ」
途端に、ユーディリアの眉がつり上がった。
「リカッロ、わたし、今日はできるだけ一人で過ごしたいと思っておりますので、どうぞ、お引き取りください」
すっくと立ち上がり、ユーディリアは夫の前から姿を消した。
残されたリカッロは、やれやれ、と頭を掻いた。
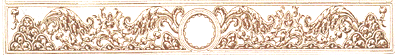
(もう、イライラするなぁ!)
部屋に戻ったユーディリアは、ぞくりとするような寒気を感じ、寝台に横たわった。
『体調は、大丈夫ですか?』
心配そうにリッキーが覗き込むところへ、この裏切り者、と呟く。
『ね、ほら、そうでしょ?』
『まぁ、確かに、聞いていた症状と合致するのぅ』
遠くで会話するベリンダと将軍が、いつになく仲良しなのも何だか気に入らない。こっちは頭痛に吐き気に、とうとう寒気まで襲って来たって言うのに。
「あの二人は、何の話をしているの?」
『もちろん、姫様のことです。すみません、やっぱり妊娠している身体で荒事はいけませんでしたね』
「……はい?」
遠くで、『あ、こら、バカ』『まったく口が軽いのぅ』と二人の声が聞こえる。
「ごめんなさい、リッキー。今、何て?」
『え、あ、あぁっ!』
自分の失言に気づいたリッキーが慌てて手をバタバタさせ、助けを求めるようにベリンダと将軍に目を向けた。
『あーあ、自分で気づくまで待とうって言ったじゃない』
ベリンダが、軽く肩をすくめて寝台に寄って来た。
『ユーリ、自覚はなかったかもしれないけど、おそらく妊娠してるわよ』
「え……?」
言われて日数を数える。そして、体調不良からでなく青くなった。
「うそ……」
『嘘じゃないわ。その症状は明らかに「つわり」よ』