2.魚心あれば水心
「あぁん?」執務机でサラサラとペンを走らせていたリカッロは、ガラの悪い声で聞き返した。
「もう一度復唱いたしますか?」
ユーディリアの部屋付きのメイド、ハンナは臆すことなくリカッロの目の前に立っていた。
王妃の伝言を持って来た彼女は、もう幾度となくユーディリアからリカッロへの啖呵を伝言として持って来ている。今更リカッロに睨まれたからと言って、脅えたりはしない。
「王妃様はしばらく翠の間で過ごされるそうです。そのことについて陛下に伝言を承りました。『しばらく顔も見たくないから、絶対に来ないで』とのことです」
淡々と言い切った年かさのメイドの言葉に、動揺したのはリカッロだけではない。副官ボタニカも過去にない明確な拒絶に目を丸くした。
「……その発言に至る理由は?」
「承っておりません」
年かさのメイドの言葉に、ちっ、と行儀悪く舌打ちしたリカッロは、手振りで「戻っていい」とハンナを下がらせた。
「……」
タイミングからして、新兵との立ち会いの件だろうか。
「……」
その後、将軍から解説を聞きたいと言ったのが疳に触ったのだろうか。
「……」
「さっきから、視線がうるさいぞボタニカ」
今度は何をやらかしたんですか、と言わんばかりに目で責められ、リカッロは副官をギロリと睨んだ。
「今更、私が何を言っても仕方ないでしょう。ですが、早めに治めてください」
褐色の肌の副官は、それだけ言うと、自らの手にした書類に目を落とした。
「ちっ」
リカッロも再び手元の書類――歳費一覧に目を落とした。ユーディリアのことは気になるが、だからと言って仕事を放り出すわけにもいかない。
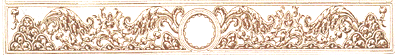
夫婦喧嘩はいつものことだし、城内別居も二、三日だろうとタカをくくっていた城内の人間の予想を大きく裏切り、王妃の籠城は一週間過ぎた今も続いていた。
これはよほどのことがあったのに違いない、とある者はリカッロに嫌疑の表情を見せ、中庭での王妃の歌声を楽しみにしていた者は落胆の日々を送っていた。
だが、一番の被害を被っていたのは、他ならぬリカッロだった。
「……っくそ」
今日の執務を終えた彼は、足取り重く自室へと向かっていた。
「足りねぇ……!」
自室のある三階へあがると、苛立ちに任せて壁を蹴った。そしてチラリ、とユーディリアが籠もる「翠の間」へ続く扉に視線を送る。
そこは、かつてユーディリアとその夫となる筈だったハルベルト王子が過ごすための部屋だった。一時期はリカッロとユーディリアもこの部屋で寝台を共にしていたが、今は別の部屋を使っている。
「ふざけるなよ。今さら……!」
リカッロは翠の間の隣、主のいない部屋へと入る。
苛立ちの原因ははっきりしていた。
それを言葉で表すとすれば、―――嫁成分不足だ。
リカッロは部屋を突っ切りバルコニーに出ると、月明かりをたよりに、手すりに足をかけ、隣室のバルコニーへと飛び移った。そして、窓から翠の間へ侵入を果たす。
ちなみに窓の鍵は、事前にメイドに言いつけて、こっそり開けておいてもらっていた。さすがにメイドの方も、この長い籠城期間に危機感を持っていたのだろう。すぐに了承した。
「将軍、ベリンダ、リッキー。悪いが邪魔するぞ」
見えない彼らに声をかける。
妻に声をかけないのは、健やかな寝息が聞こえているからだ。
今宵は手燭も要らない満月の夜。窓から差し込む光だけで十分だった。歩き慣れた間取りを迷いなく寝台に向かう。
「……」
ようやく視界に入った穏やかな寝顔に、リカッロは思わずため息をついた。
起こしてやろうか、と手を伸ばす。
だが、直前で考えを変え、延ばした手で長い蜂蜜色の髪を一房すくい上げた。
「……何が気にくわねぇんだよ、お前は」
愚痴をこぼし、そっと髪に口づける。ふわり、と石鹸の匂いが漂った。
「別に、気に食わないワケじゃないのよ」
ぎょっとリカッロが身を引いた。今のは、紛れもなくユーディリアの声だった。だが、寝起きの悪い彼女が、起き抜けにそんなハッキリと物を言えるわけがない。
①最初から起きていた
②寝言
③実は寝起きが悪いのは演技
とりあえず、思い浮かべた選択肢のうち、③だけはないと消去する。
「ゴメン、陛下。驚かせるつもりじゃなかったの」
再度、ユーディリアの唇が動く。だが、その目は閉じられたままだった。
今度は、リカッロは驚かなかった。自分のことを陛下と呼ぶのは妻ではない。
「ベリンダか?」
「そう。ユーリが眠ってるから、ちょっとだけ身体を貸してもらったの。って言っても、大きく動いたりするとユーリが起きちゃうからね、口元だけ」
とりあえず、①でなくて良かったと胸をなで下ろす。
「……ベリンダ。お前達は、ユーリが籠城している理由を知っているのか?」
「もち。あったりまえじゃない。だからって、ここでバラすわけにはいかないけど、アドバイスだけはしたげる」
リカッロは無言で続きを促す。
「昼間に堂々と扉を蹴破って、そんでもって真正面から問い詰めれば、きっと白状するわよ。ユーリ自身も、かなり、なんてゆーか、グダグダだし?」
「……そうか。それならやってみよう。―――ただ」
リカッロはユーリを見つめる。
「それはそれとして、一旦、出てもらえるか?」
「えー? あー、もしかして、そーゆーコト? まぁ、いっか」
承諾したベリンダが本当にユーリの中から出て行ったのか、確かめる手段はない。リカッロはゆっくり三つ数えると、仰向けに眠るユーディリアの背中に手を差し入れた。
戦場で同胞を抱え運んだ経験豊富な彼にとって、彼女の身体は心配になるほど軽い。
上体を少しだけ浮かせると、そのまま、ぐっと抱きしめる。
力なく垂れる腕は、彼女が覚醒していないことを示している。
リカッロはそのぬくもりを吸収するように、優しく抱きしめた。
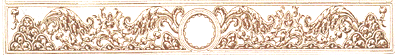
「お、終わった~」
気の抜けた声を出したユーディリアは、白い木綿の布を木枠から外した。
最後の一枚をばさりと広げ、仕上がりに問題ないことを確認すると、ひとつ強く頷いた。
「これなら、大丈夫でしょう」
丁寧に折り畳み、既に完成していた三枚の上に重ねると、ぐぐっと大きく伸びをした。肩のあたりがベキバキと音をしそうなぐらいに凝り固まっている。
メイドに頼んでお茶を入れてもらおうかと考え―――凍り付いた。
「陛下、どうかおやめください!」
「うるせぇ、すっこんでろ!」
階段をあがる騒がしい靴音とともに、そんな主従のやりとりが近づいて来る。
ゴンゴンゴンッ
ノックと言うには荒々しい音に、ユーディリアはビクッと身体を震わせる。
「いい加減に出て来い、ユーリ」
「陛下、もう少し穏便に―――」
おそらくボタニカだろう、何とか宥めようとするも、うるせぇ黙れ、と一蹴されている。
(ど、どうしよう……)
慌てて室内を見回すが、こんな時に限って、三人とも姿を見せない。
とりあえず、何とか帰ってもらおうと口を開く。
「リカッロ。しばらく顔も見たくないと言ったはずですわ。それに、まだ執務をするべき時間ではありませんの? もう国王となって一年にもなるのですから、あまりボタニカの手を患わせるのはよろしくありませんわ」
毅然と言い放っておきながら、ユーディリアは足音を殺して、そろり、そろりとドアから離れ、バルコニーの方へ移動する。いつぞやのように、隣室のバルコニーから移って来られても困るから、窓をしっかり閉めておかないと、と考えてのことだ。
ドア越しに「陛下、さすがにそれはっ」とボタニカの慌てた声が聞こえたかと思うと、ドガンッと大きな音が響きわたって、ユーディリアは信じられない物を目にした。
「ボタニカ、邪魔すんなよ」
文字通り、ドアを蹴破ったリカッロが、獰猛な表情でユーディリアを睨みつける。
(う、うそ……)
「で、出て行ってください」
窓を背にしたユーディリアの声は、小さく震えていた。
「お前の要求を聞く気はない」
低く響くその声に、リカッロのいつにない怒りを感じたユーディリアは、無意識に後ずさる。
(い、や……。今はまだ顔を合わせたくないのに……っ!)
恐怖に混乱した頭で、どうにか逃げる方法はないかと考える。
そんなユーディリアを追い詰めるように、リカッロはゆっくりとした足取りで、確実に距離を詰めて来た。
(廊下に通じるのは、あのドアだけ。でも、脇を通り過ぎるなんてできないし、……あっ!)
自分が何のためにバルコニーの方へ足を運んでいたのかを思い出したユーディリアは、くるりと彼に背を向けるとバルコニーに躍り出た。
隣室の窓が開いているかどうかは知らないが、それに賭けるしかない。
手すりに手をかけ、ぐっと反動をつけてから足を引っかける。ドレスの裾がまくれて足が見えてしまうのなど、気にしている余裕はない。
手すりの上に乗った左足をぐっと伸ばして立ち上がろうとした時、腰に何かが絡まった。
「きゃうっ!」
およそ貴婦人に似つかわしくない妙な悲鳴が口からこぼれる。
―――そして一瞬後、ユーディリアの身体はリカッロによって拘束されていた。