4.雨降って地固まる
「今、何て言った……?」我ながら間抜けな声を出したものだと思う。
「何って、……あ」
目一杯の抵抗をしていたユーディリアが、まるで絶望という名の崖っぷちに立ったような顔をして、全身から力を抜いた。
リカッロは今の言葉を、一言一句間違えずに頭の中でリピートした。
聞き間違えたのだろうか。
もし、今の言葉が本当だとしたら、目の前の妻の行動の意味が分からない。
珍しく混乱する彼を救ったのは、その混乱に陥らせた張本人だった。
ユーディリアは涙のたまった瞳で、キッと鋭く夫を睨みつけた。
「―――お互いに」
自分の口から震える声が漏れたのを嫌がったのか、一度、言葉を止める。だが、もはや止められるものではないと諦めたのか、再び口を開いた。
「お互いに政略結婚と知った上で夫婦になりましたよね、わたしたち。後を継ぐ子供さえできれば、別に無理に仲良くしなくてもいいですよね? ですから、もっと恋愛ごとや睦事に長けた愛人も作ったらいいと思いますの。それに、リカッロだって、国元に一人や二人、女性の方がお待ちでいらっしゃいますわよね? その方々を呼び寄せて側室でも何でもお持ちになればいいと思いますけれど、どうお考えですの?」
とんでもなく早口に、しかもノンブレスで言い切ったユーディリアの口から荒い息が漏れる。ついでに先ほど舐め取ったばかりだというのに、涙もこぼれた。
「ユーリ」
信じられない気持ちで妻の名を呼ぶと、再び睨まれた。
「別にあなたが何人の女性を側に置こうと、わたしが王妃としての責務を放り出すことはありませんから、心配なさらないでくださいな」
ぼろぼろと涙をこぼしながらも、その口から出る言葉は王族としての矜持に終始する。
「……ユーリ、いいから落ち着け」
「この上もなく落ち着いていますわ。政略結婚なんて、子供さえできれば、後はお互い好き勝手できるなんてこと、百も承知ですもの。いまさら動揺する理由なんて―――」
リカッロは自分の手で暴走する妻の口を押さえ込んだ。言葉の奔流が止まったのを確認すると、手を放し、一語一語区切って言い放つ。
「少し黙れ」
有無を言わせぬ迫力に負け、ユーディリアは口を閉ざしうつむいた。だが、涙は止まらないのだろう。いくつかの滴が床に落ちて行く。
リカッロは大きく息を吐いた。
自分の中で暴れ出す感情を押さえ込む。とにかく、冷静に順を追って整理する必要がある。
「まず、妊娠したのは間違いないのか?」
「……えぇ。今日、城付きのカルディア医師にも診てもらいましたので、間違いないと思いますわ」
ユーディリアの沈んだ声は、淡々と事実を述べる。
「お前は、子供が欲しくなかったのか?」
「いいえ。たとえ異能を持って生まれるかもしれなくても、嬉しくないわけがありません」
これだけは疑って欲しくない、と示すように、ユーディリアは顔を上げ、まっすぐにリカッロの瞳を見つめた。
「―――だって、あなたとの子ですもの」
その言葉に、表情に、嬉しさや面映さが一周回って殺意すら覚えた。
(それは凶悪すぎるだろ……っ!)
うろたえる自分を見られたくなくて、リカッロは妻の体を抱きしめ、彼女の顔を自分の胸に埋めた。せっかく押さえ込んだ「嬉しい」感情が今度は止めようもない間欠泉のように吹き出す。自分の顔がだらしなく緩むのさえ止まらない。
深呼吸し、息を落ち着ける。表情筋を何とか支配下に置いたところで、交わした会話を思い出し、現状を把握すべく頭を回転させた。
「同情で、……こういうことをするのは、やめてください」
弱々しい拒否が腕の中から聞こえる。
何から伝えればいいか分からないが、とりあえず言ってやりたいことはあった。
「お前、恋愛音痴もたいがいにしろよ?」
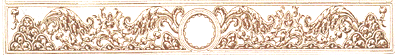
もう、ぐちゃぐちゃだった。
せめて物わかりのいい妻でいようと、頑張ったけれど、ダメだった。
自分ばかりが相手のことを好きでどうしようもない。
(本当は、すごく、イヤなのに……)
自分以外の女の人が、この逞しい腕に抱かれるのを想像しただけでも泣きたくなる。
でも、自分のことを好きでもないこの人が、我慢を重ねるのもダメだ。きっとそのうち嫌われてしまう。
いつまでも、自分だけを見ていて欲しかった。
自分の、レ・セゾン王家の血を引く跡継ぎができてしまえば、後は形ばかりの夫婦になるのだと分かっていた。
でも、いざ子供ができたと分かると、それを犠牲にしてまでこのままの関係を続けようなんて気にもならない。
だって、子供の半分は、彼で出来ているのだ。
大好きなこの胸板にすがって泣けるのもこれが最後だと思うと、このまま時間が止まればいいのに、という気持ちがじわじわと心を浸食する。
だけど、それに流されることは、今まで培ってきた王女としての教育が許さなかった。
「同情で、……こういうことをするのは、やめてください」
ユーディリアは拒絶するように、両手のひらを相手の胸板に添え、ぐっと力をこめる。だが、思うように腕に力が入らない。
すると、予想もしない言葉が降ってきた。
「お前、恋愛音痴もたいがいにしろよ?」
呆れたような声。いつもの言い合いと同じく、拒絶の色はいっさいない。
「まったく、オレも明確に口に出さなかったのは悪かったかもしれねぇが、とっとと気付けよ」
何を言っているのか分からないまま、彼の腕の中で身をよじり、その表情を確かめる。
いつもの、ユーディリアをからかうような表情だった。いや、いつも以上に弾んでいるようにも見える。
「さて、恋愛音痴のお前に問題だ。オレはこの部屋に入って、最初に何をした?」
言われて、最初のやりとりを思い出す。
「バルコニーから逃げようとしたわたしを、捕まえましたわ」
「その後は?」
記憶を再生したユーディリアの頬が僅かに火照る。
「その、……わたしに口づけて、抱きしめました」
「何のためだと思う?」
(……理由?)
あの時、自分は傍目にも分かるほど動揺しきっていた。それならば、頭の回る彼のことだ、きっと―――
「動揺していたわたしを、なだめて落ち着かせるため、でしょう」
ユーディリアの回答に、夫は半眼で見下ろした。そして、本当に恋愛音痴は治らないな、と視線を逸らす。
(呆れられた―――?)
がーん、とショックを受けて、ユーディリアは呆然とした。
「一週間も避けられて、オレが何も感じないとでも思ったのか?」
言われてみれば、失礼なことをしてしまったかもしれない。好感度が下がっても仕方がない。
「お前のぬくもりが恋しかったに決まってるだろう」
言うなればユーリ不足だ、と、ニヤリと笑みを浮かべたリカッロは、唖然とする彼女の額に唇を落とした。
彼の言葉がゆっくりと浸透して、一つの解を導き出す。だが、それは都合が良過ぎるだろう、と慌てて打ち消した。
「り、リカッロも健全な男性ですもの。女性の肌身が恋しくなるのは、別に変なことでは、ありません……わよ、ね?」
自分でも何が言いたいのか分からないまま、あわあわと心に浮かんだ二つ目の解を口にする。どこかで聞いたようなセリフ回しになったと思えば、最近読まされた恋愛小説にこんな感じのセリフがあった。
(そう、男性は、禁欲的な生活を送っていると、女性の肌が恋しくなる、って……)
リカッロの表情が、少しだけ険を帯びた気がする。
「まったく、どう言えばきっちり伝わるんだ? 直球は好みじゃねぇんだけどな。―――いいか? オレはお前以外に嫁を持つ気はねぇし、愛人も作る予定はない」
「え……?」
「お前以外を抱かない、とまでは言い切れないがな。ついムラムラと来る時も―――」
「だ、ダメですっ!」
それが自分の声だと気づくまでに、若干の遅れがあった。だが、思わず反射的に口をついてしまった言葉に、ユーディリアの顔がみるみる赤く染まる。
「ようやく本音が出たな」
「べ、別に本音とか、そんなのじゃありませんから……っ!」
「へぇ? じゃぁ、オレが高級娼館に通っても文句はねぇな?」
(本当にこの人はいじわるだ……)
こっちの気持ちを分かった上で、こんなことを言ってくる。でも、そのセリフを肯定することはできない。
「ダメ……です! 確かに、わたしは恋愛感情に疎いかもしれませんし、その、そういうことでリカッロを満足させることはできないかもしれません! でも、イヤなんです! ダメなんです!」
まるで駄々っ子のように感情的に声を上げてしまってから、激しく後悔した。物わかりのいい女を演じる作戦が、すべて崩れてしまった。
(愛人にも寛容な妻でいようと思ったのに……!)
かと言って、いまさら元の路線に戻ることなどできない。どうすればいいのかとアワアワしていると、妙な言葉が聞こえた。
「まったく、お前はオレを殺したいらしいな」
どうしてそういう発言に繋がるのだろう、とリカッロを見上げると、彼はユーディリアの見たこともない表情を浮かべていた。
「リカッロ……?」
口元は笑みの形を作っている。いつものような意地悪でない、純粋な微笑みに見えた。目元がうっすらと赤いような気がする。そして、どことなく困ったような瞳。
おそらく、笑み崩れる、と言った表現が適当なのだろう。
「オレの前では、王家の女として施された教育は忘れろ。そんな風に本心を口にしていい」
「忘れる、なんて―――」
「あぁ、そうだな。王家にふさわしい女であろうと、気を張って背伸びをするお前は嫌いじゃない。だけどな、オレはお前を甘やかしたいんだ。オレの目の前でだけ、思うままに振る舞えるぐらいに」
「……」
もはや、何も言えないでいるユーディリアを見て、リカッロは笑った。
「お前には、ストレートに言わないと伝わらないみたいだな。―――愛している。そして、オレの子を宿してくれて、ありがとう」
まっすぐな言葉は、まっすぐにユーディリアの心に浸透し、彼女は―――
「……」
へなへなとその場に崩れ落ちた。
「それにしても、どうして妊娠=愛想を尽かすってことになったんだ?」
その思考展開が理解に苦しむとばかりに、妻に手をさしのべつつ、リカッロが尋ねた。
「……その、今までに読んだ恋愛小説は、どれも、政略結婚は愛のないもの、ということでしたので」
顔を見られないユーディリアは、目を逸らしたまま、夫の手を取る。
「恋愛教育が仇になったか。……難しいもんだな」
「す、すみません。なんだか、色々と……」
「あぁ、ボタニカにも謝っておけよ? お前に触れられなくてイライラしっぱなしだったオレに八つ当たりされた、可哀想な被害者だからな?」
リカッロは加害者である自分を棚に上げ、ぬけぬけとそんなことを言う。だが、確かに悪いことをしてしまったと思うので、後で謝っておこう。
「今度はよけるなよ? さすがにオレもショックだったからな」
近づいてくる夫の顔に、小さく「はい」と答えたユーディリアはそっと目を閉じる。
そして、温かく柔らかい感触に酔わされるように、大好きな彼の胸に体を寄り添わせた。
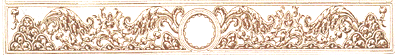
『ね、ほら、やっぱり二人きりで話すのが一番だったじゃない』
『途中、ハラハラしたがのぅ』
『そう? だって、どう見たって相思相愛じゃない。よほどのすれ違いがなければ、破局なんてしないわよ。ねぇ、リッキーもそう思うわよね?』
『ずいぶん前からおらんぞ?』
『え、なんで?』
『恋愛事には興味がないと言っておったからのぅ。どうせ城内をうろついているんじゃろう』
『もー! かわいいユーリの一大事なのに!』
『のぅ、歌姫殿。歌姫殿が国王の想いをさらっと暴露すれば、ここまでこじれることはなかったと思うが』
『こういうのは、本人達が解決すべき問題でしょ?』
『まぁ、その考え方は否定せんが、どうにも歌姫殿が自分の趣味で動いているように思えてのぅ。悪趣味だとは思わんか?』
『こんなおもしろいドラマを見逃せって言うの?』
『……』
『だいたい、そんなこと言うなら、どうして将軍もこうやって二人のやりとりをこっそり観察してんの? あたしのことを悪趣味だって言うなら、将軍だって悪趣味じゃない』
『単なるおせっかいで見守っていただけじゃよ。国王が逆上して暴力に走るようなら、助けに入ろうと思って、な』
『それ、陛下と手合わせする機会を逃したくないってハナシよね? 将軍だって人のコト言えないじゃん』
『……まぁ、の』
『もー! 自分のコト棚に上げて!』
『どちらにせよ、もう大丈夫そうじゃな。儂はもう離れておくわい』
『……そうね。もう、あとは、砂を吐くような展開が目に見えてるしね』