5.心腹の病
「狭い」
第一声に、摩耶の口元が
「一人暮らしにしては広いんだけどね、このマンション。何にしろ、鍵を
かつては家族三人で暮らし、娘の親権とともに勝ち取った慰謝料をけなされて思わず反論が口を突いて出る。
相手は一般庶民の生活を知らない坊ちゃんなんだから、と自制しながらいささか性急に深呼吸を繰り返した摩耶は、引き出しから小さめのTシャツとハーフパンツを探し出し、そこに自分の寝巻きとバスタオルを重ねた。
「今日は早いところお風呂入って寝ましょ」
「……」
声をかけられた悟は、まるで聞こえなかったかのようにリビングのソファに腰を落ち着けた。
「どうしたの?」
「僕は入らないぞ」
「は? ―――下着の心配してるんだったら、さっきコンビニで買ったじゃない」
「入るとしても、一人で入るからいい」
その言葉に、ようやく彼の言いたいことに気づいた摩耶は、微笑みそうになる口を気力だけで止めた。
(なんだ、恥ずかしがってるだけじゃない)
ふと、意地悪したい気分がむくむくと湧いてくる。
彼女はマンションを
「あのね、あたしは君を守るのが仕事なの。それが食事中であろうが、……入浴中であろうがね」
悟はぐっと口元に力を入れるが、反論の言葉は出てこなかった。
「ってことで、さっ、入ろうか!」
力尽くで悟を脱衣所まで引っ張った摩耶は、嫌がる少年の言葉を無視して、えいやっと服をはいだ。
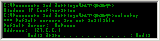
「発信器は付いていなかったのか?」
辱めに耐え、用意された布団に潜り込んだ少年は、
「何のこと?」
「脱衣所で僕の服を確認してただろ」
妙に観察眼の鋭い悟に、摩耶は少しだけ仕事のやりにくさを感じる。だが、護衛対象の不安を取り除くのも仕事のうち、と隣の布団でごそごそと悟の方に向き直って答えることにした。
「なかったわ」
「家のヤツが付けた物もか?」
「あれは、護衛を引き受けた時から外してもらってるわ」
「なんでだ?」
「発信器は電波を出してその存在を教える物よ。その周波数が洩れていた場合のことを考えて? 役に立たないどころか、足手まといになるだけ、……そうでしょ?」
常夜灯の薄暗い灯りの中、悟が苦い顔をするのが見えた。そんな危険なものを今まで付けられていたのか、とでも言いたげに。
「勘違いしないで。別に情報が洩れていなければいいのよ。ほら、羽谷さんみたいな人がいれば、まぁ、大丈夫とは思ったんだけど。―――それでも、仕事として請け負ったからには、自分の関与できない穴を作りたくなかったの」
(チームプレイとしては、失格と分かってるのよ。それでも、侮られたままで、同じ『チーム』としては考えたくなかった)
青臭い自分のプライドを自嘲するように笑うと、それを別の意味に解釈した悟がニヤリとする。
「羽谷は苦手だろ? そんなヤツでも誉めるんだな」
「苦手、ってことは否定しないわ。でも、誉められるだけの力量があるのは分かっているもの」
おどけた表情をして見せれば、悟の笑みが様相を変える。もしかしたら、初めて見た皮肉でない笑みだったのかもしれない。
「あたしからも質問させて。どうして邸でガスが効かなかったのか」
摩耶の問い掛けに、悟の顔から笑みが消える。彼は布団の中で体勢を変えて仰向けになり、視界から摩耶を追い出した。
「僕は……昔は病弱だったからな。小さい頃は色んな薬を投与されて生きてた。だから、耐性ができてるみたいだ」
十歳の子供が「昔」なんて言葉を使うと非常に違和感がある。だが、子供の感じる時の流れでは、ほんの二年前でも「昔」と言えるんだろう。
(だから、「墓場はずっと目の前にぶら下がってた」なんてセリフが出てくるのね)
憐れみの混じった複雑な表情は、まっすぐ天井を見上げている悟には見られなかった。
「今は大丈夫なの?」
「もちろん。手術で治った」
淀むことのない声は、それが紛れもない真実なのだと教えてくれて、摩耶はホッとする。
「今度は僕から質問だ。……お前の過去について」
え?と聞き返す間もなく、悟は布団から手を出して人差し指をある方向に突きつけた。
「あの棚の上にある写真、あれが―――」
「由佳里、あたしの娘よ。でも、居場所が分からない」
相手が娘と同じ年の子供だったからか、それとも、ずっと誰かに話してしまいたかったからか、もしくは、その両方か。彼女自身、すんなりと涙を交えずにするりと答えられたことに驚いた。
「どうして、だ? 何があった?」
「離婚した旦那がね、あの子をどこかに……どこかに捨てて来たの。たぶん、親権を取られた腹いせ、だったんだと思うわ。まったく、何を考えているのか分からないわよね。自分の娘を、まだ六歳の子を―――」
自覚があるのか、消え入るように小さくなっていく彼女の声に、悟はそれ以上の言葉を飲み込んだ。
(四年。―――絶望的じゃないか)
少し話を聞いただけの悟でさえ思う。だが、気丈にも探し続けている彼女の不安は推し量ることはできない。
「もういい。眠い。おやすみ」
「……えぇ、おやすみなさ」
それきり、沈黙が落ちた。
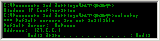
こん、こん
―――時は前後して、見事脱走した二人が電車に揺られていた頃。
二人の逃走の知らせに焦る立川の私室のドアを、誰かが叩いていた。
こん、こん
優しすぎるその音は、どちらかと言うと荒事が得意な人間が
「しつこい。開いている、入れ」
(―――いや、待て)
あんなノックをする人間が邸内にいるのか? そもそも立川が待つのは逃走した二人の行方を知らせる報告だ。それが、こんな落ち着いた様子で、などと。
「では、失礼いたしますわ」
入室して来た人物は、立川の知らない女性だった。
喪服のような黒のワンピースにジャケット。同色のストッキングにヒールで固めた女性は、濃いアイラインが少しそぐわない印象の地味な女だった。厚めの唇は暗めのルージュが塗られている。
記憶の糸をどれだけ
「あら、わたくしのことをお忘れですの? たった一度きりしか直接お会いしていないとは言え、それもほんのこの間のこと。哀しいですわ……」
怪訝な表情を浮かべた立川の心の内を読んだのか、女性が嘆きを口にする。その仕草がいやに
「貴方のような整った顔立ちの女性を、そうそう忘れることもないと思いますが、おかしいですね……」
口ではそんな弁解をしつつ、立川は警戒を
(この女、いったい誰がここまで通した?)
整った顔立ちなんて、と恥じらう様子を見せた女性は、立川の顔に疑念が広がっていくのを見とめて、にっこりと微笑んだ。
「ようやく思い出して下さいました? ―――一度だけですが、
(女装? そんな趣味の取引相手など―――)
「ま、さか、……キラーショウ?」
呟くような小さな声だったにも関わらず、相手はそれを拾い上げて「その通りですわ」と
以前、顔合わせをした際は、「どぶネズミ色のくたびれたスーツ姿のしがないサラリーマン」という風体だった。性別含めて百八十度も違う今の外見に、分からないのも無理はない。
「貴方の所の人から、突然の電話をいただきましたので、以前と同じ格好では来ることができませんでしたの」
「―――貴方は、本当のところは男性なのか? それとも」
「そんなことは、わたくしの仕事に関係ありませんわ。それよりも急用とは?」
終始にこやかだった女の顔は、「仕事」の話になると急に
「う――いや、標的の説得に失敗した。できるだけ早く仕事をお願いしたい」
「あら、交渉は決裂ですの? あの坊や、思った以上に……」
「あぁ、クソガキは頑なで、あの看護婦も
苦虫を噛み潰したような立川の表情に、ふぅん、と女は気のない相槌を打つ。
「できればあの看護婦も一緒に消せ。ただの看護婦ではないようだ」
「ただの看護婦ですって? あの安威川という女性はボディガードですわ。確かに看護師の経験はあるようですけれど」
女=キラー・ショウの言葉、その情報の速さに驚いた立川だが、すぐに平静の仮面を取り繕った。
「ボディガードなら話は早い。私が首謀者と言える生き証人には間違いない。すぐに消せ。報酬は五百万上乗せする」
女は「もちろん、承諾いたしました」と頭を下げた。