1.小舟 の宵拵 え
「
それはいつもと何も変わらない夕食の
「
食事を口に含んでしまった少年は
「医師の手配がつきました! できる限り、食べた物を
「誰か、手の
───悟・早川 十歳ト五ヶ月半。
適切カツ
原因ハ 夕食ノグラタン中ノチーズニ 含マレテイタ毒物。
毒物ノ種類ハ 特定デキズ。
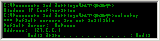
ドンッ!
いかにも高価そうなマホガニーの机が、
「生きているっ……! 生きている、だと?」
彼の
だが、彼を知る者十人に、今の彼のただならぬ様子を見せれば、八人は「信じられない」と自分の目を疑うに違いない。残りの二人でさえ「そういう人間だと思っていたよ」などとうそぶく筈だ。何しろ彼の一般的イメージは「冷静・冷徹・冷酷」の三つで表せるから。
『
たったこれだけの報告の電話で、彼はこんなにも
「あの! しぶとい! クソガキめ!」
窓には
(やはり、毒などという
早く次の手を打たなければ、という思考を邪魔するかのように、ブルルルル……と携帯電話が震える。
「
自らを立川と名乗ったその男は、電話を手にしたまま凍りついた。
『どうも、聞きましたよ。失敗したそうですね』
『どうします? 時間がないのでしょう?』
電話の相手が何をほのめかしているのかは、十分に理解していた。以前の電話では、こともあろうに殺し屋の
立川は考える時間を惜しむように腹をくくった。一度手を染めてしまったからには、最後までやり遂げねば、と。
「失敗したアイツと同額、いや、二倍払おう」
ここで彼の声に興奮が混ざっていたとしても仕方のないことだろう。今度こそ、という思いが強いのだ。
だが、冷静さを失ったわけではない。自分から交渉を始めて、なるべく低い金額で収めてしまおうと考えるだけの頭はある。
『三倍の千五百万で手を打ちましょう。もちろん成功報酬で結構ですよ。失敗した彼と同じにね』
立川が「それでいい」と承諾すると、電話はすぐに切れた。そこでようやく『ある事』に気づいた彼の身体がぶるっと震える。
(アイツが成功報酬で五百万とは、……誰も知らない筈だ)
不安と同時に安堵が広がる。だが、彼が自分の心の動きに気づくことはなかった。
彼自身、自分の心に広がっているのは
事の始まりは
いや、当事者にしてみれば、そんな小さな出来事でもないだろうが、地球の
「
早川グループを統括する
早川源五郎は不用意な言葉を決して口にしない人だと知る社長、重役の面々は政権交代の日が近いことを悟った。この白い
―――いったい誰が後継者となるのか?
重役たちの腹の探り合いによって出揃った勝ち馬予想は、以下の通りだった。
本命、今現在、総帥の片腕とも言うべき立川
対抗、観光分野の社長を務める
立川は早川源五郎と同等、いやそれ以上に仕事に厳しい人物で、用いる手段は時に冷酷なものだった。対する水島は温和な性格で、彼がトップに立てば早川グループは目覚しい発展こそないが、急落もないだろうと噂されていた。
この二人以外の候補は誰も決め手に欠けていて、似たりよったりだ。
だが、大穴に挙げられた総帥の孫、早川悟(十歳馬)が問題である。おそらく、誰かが冗談半分で名を挙げた予想なのだろうが、なかなかどうしてこの大穴はコンピュータ操作と、株の流れを読むことに関してはスペシャリストと言ってもおかしくないほどの少年だった。実際に、源五郎も孫の言葉を重く参考にしているとかしていないとか、噂の
さらに運の悪いことに、本命馬の立川は他の馬に勝つ自信を持っており、万が一負けたとしても悔いはなかった。この大穴馬を除いて。
十歳の生意気なガキに負けることだけは許せないと思いつめた結果、彼は毒殺を試み、そして、失敗したのだ。
彼は、謎の電話相手の手引きにより、新たな暗殺者と契約しようとしていた―――
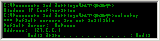
「お願いです! どうかこの依頼を受けてください!」
いかにも気の弱そうな男が、声を高くして頭を下げた。
身なりは普通のサラリーマンのようにスーツ姿で整っているが、その顔は今にも泣き出しそうなほどに歪んでいた。
「いやです。そんなこまっしゃくれた
彼とガラス製のテーブルを挟んで座っている女性は、にべもなく断った。黒いスーツに同色の体とスカート。ジャケットの下に来ているブラウスこそ白いものの、まるで喪章のように黒いネクタイをしていた。
個人企業家の集う貸しワーキングスペース。打ち合わせのために開放されている応接スペースにその二人は居た。
「あなたしか頼れる方がいないのです。どうか!」
あなたしか、と言われると、まず十人中八人は良い気分になるに違いない。きっと自分という存在の必要を確認できるからだ。そして、この女性も例外ではなかった。
(そうね。そこまで言うのなら――)
「何しろ、あなたは女性の中では最も優秀な
「聞き捨てならないわね!」
彼女の心の中で傾きかけた天秤は、全く反対にガクンと落ちた。
「何なの、その女性の中でっていう限定! 元々女の少ない業界で、それは誉め言葉にもならないわ。いったいどういう選択基準なんですか。……えぇ、よろしいでしょう。そちらがその気なら、あたしはこの依頼は断らせていただきます!」
がぁーっとまくしたてる剣幕に、男はおどおどしながら膝上の書類に目を走らせる。
(しまったぁっ!
上司のありがたい注意書きをよく読んでいた筈なのに、どうやら知らず知らずのうちに読み飛ばしてしまったらしい。
「帰ってください」
激情を隠すことなく、彼女ははっきりきっぱり怒っていた。
(や、やばい……)
男は慌ててハンカチを取り出し、額の汗を拭うフリをした。いや、実際、汗は出ていたのだが「言葉に困った時は額の汗を拭え」という
「いや、決して悪い話ではありません。この通り、契約料も破格でして、護衛中に傷を負った際の補償もしっかりと整っておりますし……」
言葉を重ねつつ、男は書類を差し出した。そして、上目遣いで相手の様子を見る。どうやら、一応興味を持ってくれたらしい。
(ふぅ、よかった……)
そんな彼の安堵を後押しするように、彼女は穏やかな眼差しで書類に目を通していた。だが、ゆっくりと彼に言い聞かせるように感想を述べる時になると、何故かその瞳は冷たい光を帯びていた。
「ふーん。『
(あぁっ! 注意書きの方を渡して……しまった!)
「す、すみません。こちらです!」
慌てて手引書を奪うように取り返し、今度こそ本物の契約書を出す。その顔は哀れなほど青ざめていた。
「いいわよ、もう見る気はないから」
(ひぃ、もうおしまいだぁ~…)
そう覚悟しつつ、彼は再び手引書に目を落とした。そして、救世主のような見出しを見つける。
『9.
「えぇ、その、もし無事に仕事を完遂された場合には、その成功報酬としてですね、その……」
「お金ならいらないわ」
彼は「うっ」という顔で怯んだ。だが偉いかな、彼は懸命に言葉を続けた。
「もちろん、金銭的な成功報酬もあります。ですけど、えぇと、契約書のこの項ですね。あなたの探し人を会社の総力を結集して捜索いたします」
男はそれだけ言って、契約書の条項に人差し指を置いたまま動きを止めた。視線もその一文に落としたままで相手の反応を待つが、聴覚に頼る限り、相手に動いた気配はない。
男は恐怖を押し隠して顔を上げた。
「ひぃっ」
思わず情けない悲鳴が口からこぼれる。
無理もない、目の前にナイフがあったのだ。
「どこで聞いたの……?」
音もなくナイフを取り出していた摩耶は、まっすぐに男を睨みつけていた。
「い、いえ、あの、私は契約書とこのマニュアルを渡されて、うまくやってこい、ってそれだけなんですよぉ……。ほら、えぇと、これです、ここに書いてあるでしょう……?」
情けないほどに震える手で差し出された手引書の冒頭には、こう書き記してあった。
『この手引書は、摩耶・安威川を穏便かつ迅速に悟様のSPに迎えるためのもので……』
「ね? ね? 本当でしょう? それで探し人のことと『キラー・ショウ』のことさ匂わせれば大丈夫だって、ほら、この項目に」
ナイフを彼に向けたままで、この失礼極まりない手引書に目を向けた摩耶は、顔をしかめた。そもそもこの手引書だって、気の弱いこの男に交渉させることで自分に見せるよう仕向けた感じさえした。キラー・ショウに関する記述を読みながら、すっかり脅えきってしまった交渉役の背後にいる人物に不快感を覚える。
(相当な食わせ者ね)
自分の生活と秘密を(二つも)知った上で全てを計画し、この不甲斐ない男を送って来た見ず知らずの人物に、同じくらい狡猾なキラー・ショウのことも思い出し、さらなる不快感に口元がひきつる。
それでも、彼女は依頼を受ける旨を伝えた。
マニュアル通り「詳しいことは後日あらためて」という言葉を最後に男が去った後、彼女は応接スペースで虚空を見上げてため息をついた。
護衛するのは悟・早川。十歳。跡継ぎ問題で早川グループの水面下がざわついている余波を受けたものと思われる。毒殺は未遂に終わり、相手は次の手段にキラー・ショウという確実性の高いものを選んだ、らしい。実際にキラー・ショウからの「
成功報酬は、摩耶がずっと探しているあの人の捜索。
そこまで頭の中に刻み込んで、男の置いて行った書類の
「キラー・ショウ……、ね」
呟いた彼女の目に映っていたのは、白い天井ではなく、何年も前の、しかもほんの一瞬の残像だった。