3.口に蜜あり腹に剣あり
「聞きたいことがある、とな」
行方不明である息子夫婦の無事祈願のために白い
ビルの高い場所に位置するこの会長室には、赤い
「はい」
短く答えた相手は一歩だけ足を進めた。夕陽を
「会長は、引退をお考えなのでしょうか?」
ダンッ
「なんじゃと?」
威圧を与えるために杖を床に叩きつけた老人がゆっくりと聞き返す。今度は老人の方が一歩分横に移動した。てっぺんだけ禿げ上がった頭に照り返す
「いえ、私が出張をしていた間、そのような話があったと伺ったものですから……」
老人が
「いや、その『自分ももう年だ』と重役連に話があったと、はい」
迫力に負けながらも相手――中年の背の高い男が答えた。
「お前にそう言ったのか?」
「はぁ」
「きっちり返事をせいっ!」
「はい、確かにそのように伺いました!」
まるで、軍隊のような雰囲気であった。
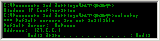
彼には嫌いなタイプが三つあった。
1.大きな力(権力や優れた能力)に媚びへつらう人間
2.何でも金銭で解決しようとする人間
3.目的の為には手段を選ばない人間
その三つを兼ね備えたとある人間に初めて出会った時から、彼はその人間から「天敵」の匂いを嗅ぎ取っていた。
本能に近い直感が騒いでいる。今回の黒幕もその天敵の仕業だと。
彼、悟はベッドから半身を起こして、手元にある端末で情報を整理していた。
「あと三十分よ」
ベッドの横に椅子を運んで座っている護衛、摩耶が急かしてきた。
(こいつも嫌いだ。僕をまるで十歳児みたいに扱って……)
少しだけだから、と口うるさい護衛を説き伏せてようやく手に入れた一時間を精一杯有意義に使おうと、返事さえ省略した。
(特に最近、大金を
彼の持つ端末には単なる数字の羅列が映っているだけに見えるが、彼自身はその数字の意味をちゃんと理解していた。
―――ハッキング。立派な違法行為である。
元々パソコンの扱いに長けていたところに、百戦錬磨のハッカー(と彼の部下が呼んでいる)羽谷からハッキングの方法を教わったのだ。羽谷は、その腕を見込まれてこの館に雇われたと聞いたことがあるが、真相は定かではない。
新たな力を手に入れた悟は、政治悪を匿名で警察やメディアに情報を流したこともあった。こんな彼は、ハッカーとしては二流・三流だと自覚している。年齢のせいかもしれないが、つい、勧善懲悪に走ってしまいがちなのだ。「必要悪」という概念は、まだ許容できない。
一通り、画面を眺めた彼は、今度は違う人間の口座を調べてみたものの、残念ながらこちらにも特に大きな金の流れはないようだった。彼の部下名義のものだが、脱税の抜け道となっていることは随分前から知っていた。
ちなみに、悟がこれを見逃している理由は「こいつだけは全ての悪事を暴きたてて一撃で打ちのめしたい」と願っているからに他ならない。その憎悪のほどが伺える。
次は、と相手の会社の方にリンクしようとして、少年の手が止まった。
(画面、が?)
何故か画面がぼやけている。新手のウィルスか、と身構えたが、真実の助け手は全く別の方向から来た。
「ストップ! あと二十八分は少し休んでからになさい」
いきなり視界を塞いだのは、女の手だった。
「何を」
するんだ、と怒鳴りかけて、ぼやけていたのは画面ではなく自分の視界の方だったと気づいた。
「それ以上は身体に毒よ。とっとと寝なさい。あたしが見てるから、安心して、ね?」
(腐っても、元看護婦か)
確かに少年の体調の微妙な変化を、即座に読み取ったのはすばらしいと思う。それでも、と考えてしまうあたり、悟はまだいじっぱりな子供だった。
「一時間、経ったら起こせよ」
ぶっきらぼうにそれだけ告げると、彼は布団を頭からかぶる。その布団の上下が一定になってから、ようやく摩耶は悟に対する緊張を解いた。
生意気とは思っていたけれど、比較的短かった看護婦人生の中では、ずいぶんかわいい方だと思う。そう許容できる摩耶だからこそ、羽谷の人選は正しかったと言えるかもしれない。
シュゥゥゥゥゥゥ……
細く空気の流れる音に、摩耶はハッと室内を見回した。
その音が通風孔から聞こえてくると気づいたが、くらくらと
館のあちこちで人が倒れ、崩れ落ちて行く。致死性のあるものではなく、単なる睡眠誘発性の毒だったことが幸いだった。
意識を保つ者のなくなった少年の部屋に、音も無く一人の侵入者が姿を現した。通風孔から這い出た侵入者は、身体にフィットしたスウェットスーツらしきものに身を包んでいた。夕闇に浮かぶボディラインから男であると分かる。
ベッドに近づいた彼は、標的の上に女性が折り重なっているのを見つけて、面倒臭そうな表情を浮かべた。
仕方なく、女性を押しのけようと肩に手をかける。
その瞬間、倒れていたはずの女性が跳ねるように飛び起きた。その手には小さなナイフ。
「あなた! キラー・ショウじゃないわね」
マスク越しのくぐもった声が、侵入者を怯ませた。
「キラー・ショウだったら、誰かの見ている前で仕事をしないと気が済まないはずよ」
侵入者は何も言わずに腰から銃を取り出し、構えた。
(銃刀法違反!)
場違いにそんなことを思いながら、摩耶の全身が緊張に強張る。
「僕の部屋を血で汚すな」
緊張した局面に関わらず、平然としたその声は他でもない、侵入者の標的だった。
「悟くん?」
よっこらしょ、と上半身を起こした悟に、摩耶が
「お前の仕事は本当に『殺し』か?」
部屋に充満する気体を物ともしない少年に、侵入者も
(こいつは、……なぜだ? 恐れる様子すら見せない――)
「墓場はずっと目の前にぶら下がってたんだ、ずっとな。図太くもなる」
そこで一拍だけ区切り、「それで、答えは?」と催促する少年はとても十歳には見えない。
「……私は招待状代わりだ」
侵入者は動揺を押し隠し、威厳を取り戻すように答えた。
少年はちらり、と摩耶を見た。だが、仕事熱心な彼女は侵入者から目も離そうとしない。
「やれやれ」
悟はおどけるように、からかうように招待状の返事を口にする。
「あいにくと、僕は病人なんだ。看護婦付きでもいいなら、招待を受ける」
看護婦、と指された摩耶はぎょっとして目を丸くした。侵入者も思ってもない条件に驚きを隠せない。だが、しばらくの
「行くの?」
摩耶の声に「もちろん」と即答した悟は、平然とベッドから立ち上がった。
(本当に、十歳なのかしら)
外見は小学生なのだが、あまりに落ち着いた態度や考え方、交渉術に至っては大人顔負けだ。
摩耶は目の前で着替える少年を凝視した。華奢な身体にまだ少し青白い顔、そして―――
(あっ)
声に出さずに驚く。悟の両手が小さく震えていたのだ。
果敢にも罠に飛び込もうとする彼が、恐怖を感じていないわけがない。
「行くぞ」
着替えの終わった彼に言われ、慌てて自分の鞄を掛けた摩耶は彼の手をそっと握った。
「なんだよ」
見上げる目が非難の光を帯びる。それでも、無理に手を離そうとはしなかった。摩耶も、震えている手を言及はしない。
二人は手を繋いだまま、侵入者の待つ外へと足を向けた。
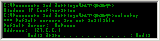
二人は館の外に止められていた車で運ばれた。
待っていた運転手に声を掛けた侵入者は後部座席に二人を押し込めて、自分は助手席に座った。下手な行動をするな、と再び銃口を向けられる。
館のある港区の住宅地から高速を使って南へ、横浜方面へと向かう。標識を見る限り、横浜市内にある某所で車が止められる。目の前には悟の館に負けず劣らずの大邸宅が
「出ろ」
助手席から降りた男が短く促した。
口を閉じるよう強制されながらも、目隠しされなかった所を見ると、よほど依頼主はよほど自信があるのか、それとも何らかの交渉に頷かない限り、帰す気がないのか。そこまで思い至った摩耶はげんなりと肩を落とした。
男に案内されて、悟と摩耶は迷路のような邸をぐるぐると回り、三階のある部屋へと通された。
部屋で待っていたのは、身長百八十はあろうかという細身の男だ。ブランド物のスーツに身を包んだ彼は、二人が入って来ても窓の外の星を見上げていた。
「連れて来ました」
案内して来た男は、退室するでもなく、廊下に繋がるドアの前で姿勢正しく立ち塞がった。
ようやく振り向いた依頼主は、摩耶を見て少し左の眉を持ち上げた。黒縁の眼鏡を鼻のところで押し上げて、ゆっくりと口を開く。
「そちらの女性は?」
「あたしは、この子に付いている看護師です」
看護師と口にしてしまったせいか、思わずかつての仕事中に浮かべた営業スマイルが表面に出てしまう。
「過日の事件から体調が思わしくありませんので、手短にしていただけると助かります」
毒殺の依頼主だろうかと当たりをつけた皮肉だったが、相手は気にした様子もない。
「……だ、そうだ。それで立川のおじさんは僕に何の用事が?」
看護師と手を繋いだままの悟は、ぎっと相手を睨みつけた。
「これはこれは、悟
「
心の柔らかい場所をえぐる言葉に、立川の顔が歪んだ。だが、それも一瞬のことで、すぐに余裕の笑みを浮かべて見せる。
「……これは、最初で最後の救済ですよ。そんなことを言ってもよろしいので?」
「見返りは? 僕に動くなと言うからには、もちろんあるんだろう?」
「―――安息と長生き。欲しいでしょう?」
四十近く年の差のある二人が、淡々と会話する様を、摩耶は見守るしかできなかった。
悟はずっと拳をきつく握り締めている。その手に浮く血管が、いつか少年の神経が切れてしまう
生まれてからたった十年。それなのに
「……」
「どうです?」
悟は大げさにため息をついた。
それを見た立川が、とうとう観念したか、とほくそ笑む。
「話にならないな」
「な……っ!」
「安息も長生きも、お前でなくとも、他の誰の手によっても破られる。僕を放っておく気はあっても、守る気はないんだろう?」
立川は答えない。
「かつての父さんのように、そんなものは簡単に破られる」
悟の父親のことを思い出したのか、立川の頬がピクリと引きつった。
「僕が父さんのように、たった一度の仕掛けで死ななくて、さぞ残念だったろう? あれは確かに致死量だった。いや、致死量はたった一口だった! だけど僕は死なずに生きている。それがどれほどお前のプライドを傷つけているかと思う……と!」
笑みさえ浮かべて声を張り上げていた悟の身体が、突然「く」の字に折れた。大きく咳き込んだ少年に、摩耶が慌ててその身体を支える。
「……落ち着いて。まだ身体が本調子じゃないのよ」
ゲホゲホと苦しそうに咳を繰り返す悟の背中を撫でながら、彼女は立川を見上げた。
「立川さん、どこか彼が休める部屋を用意していただけませんか?」
突然の申し出に驚いた立川だったが、ニヤリと笑い「もちろん」と承諾する。
「ふざけるな! こいつは僕を殺す気だ! 部屋なんて用意させてみろ! 絶対に何か仕掛けて―――」
「大丈夫よ。交渉がまだ終わらないうちはね。――そうでしょう、立川さん?」
予想外の「看護婦」の言葉に、彼は眉根に皺を寄せた。
この女は何を言っている? どう贔屓目に見ても交渉は決裂だ。決裂して終わったんだ。それをなぜ、終わってないなどと言う?
(いや、待て。……そうか)
交渉が決裂すれば、自分もこのクソガキと一緒に始末されると思っているのか。賢明な判断だ。それなら、何とかこのクソガキに要求を飲ませようとするだろう。こちらとしても、
立川はにっこりと笑って、寛大な気持ちを表すように両手を広げた。
「もちろんだ。後のことは貴方に任せよう。―――おい、二階の客間へこの二人を案内しろ」
ゼエゼエと苦しげに呼吸する悟の身体を抱きかかえたまま、摩耶は扉の前に立っていた男に先導され、客間へと向かった。
一人残った立川は、再び窓辺に歩み寄る。
「説得できれば良し、説得に失敗すれば―――二人とも始末すれば良いことだ」
土に還すか、海を堪能させるか、それはその時に決めれば良いことだ。
「早川グループは、あんなガキのオモチャにするために、私が心血を注いで大きくしたわけではない……!」
総帥の孫だからと言って、そうそう渡してなるものか。
でなければ、わざわざ総帥の自慢の一人息子を手にかけた意味がない。
「この時代、血が繋がっているというだけで、会社を継ぐなどとバカカしい。そうだろう……?」