7.引かれ者の小唄
由良ちゃんと会ったのは、四年前。
離婚して、この仕事を始めてからそんなに経っていなかったわね。
転職の理由? 別れた相手が医者だってこともあって、看護師を続けるのは何となくイヤだったし、まとまった自由な時間……
あの仕事はイヤって言うほど覚えてる。何しろ、失敗らしい失敗を経験していなかったし――まぁ、それはストーカー対策とか仕事の難易度そのものが違ってたって言うのもあったんだけど――丁度、新しい仕事に慣れて来て、緩みも出てたのね。今度も成功するんだと、疑いもしなかったわ。
その頃はキラー・ショウなんて全然知らなかったし、殺し屋なんて存在するんだ、って思ってたし、あの仕事の時も、頼りになる同業者がたくさんいたし。今思い出すと、さすがに恥ずかしいわ。
あの仕事でのあたしの立ち位置は、そうね、保母さんだったわ。
ターゲットが小五の女の子だって聞いて驚いた。でも、君の所みたいな大きいお邸だったし、そういう世界もあるんだって納得したわ。
その女の子が「由良ちゃん」。
今は、もう中学生ね。元気でやっているかしら。
本当のターゲットはその両親だった。
情報が
あたしを選んだのも遠藤さん。女性だから、元看護師だから、っていう理由で由良ちゃんの近くに配備したのね。だからこそ、この仕事以降は、そういうニュアンスであたしを不当に低く評価するような依頼は全部切ったわ。と言っても、今回は例外ね。娘のことを持ち出されるんだもの。
―――ごめんなさい、少し話が脱線しちゃったわね。
その仕事では、キラー・ショウは日時予告をしてきたの。まさかそんなことをする相手とは思わなくて、あたしは遠藤さんに噛み付いたわ。
「これって、狂言じゃないんですか?」
そしたら遠藤さんは、いつになく厳しい顔して
「
「だったら、この警備でもなめられるってことですか?」
「そうだ。
「―――冗談でしょう?」
「冗談だったらどんなにいいか。……よく聞け、相手はナイフ一本で標的だけをちゃんと殺す、そんな野郎だ」
あたしは真面目な顔でそんなことを言う遠藤さんに返す言葉もなかった。
「
その命令に、あたしは一層気を引き締めたけど、それも今考えてみれば皮肉な話ね。仕損じのないキラー・ショウに対して標的外の女の子を守っておけ、なんてね。
指定されたのは二十時ジャスト。今思い出してもあの夜の記憶は鮮明に残ってる。悪夢のような時間だったもの。
時報に合わせた時計の、チクタク動く秒針が皆の神経を尖らせて行った。部屋の中央にいる由良ちゃんは事の次第を知らされてなかったけど、周囲の大人につられて、言葉も少なかったわ。
二十時になると同時に、視界が真っ暗になった。
ブレーカーじゃなくて、屋外の配線に細工がされていたのは後で分かったわ。
あたしはとにかく、暗くなったと同時に由良ちゃんを押し倒して上に覆い被さった。いざという時は、あたしの身体で由良ちゃんを守れと遠藤さんからも指示を受けてたし、迷うことはなかった。
気配だけで、同じ部屋に詰めていた、廊下に立っていた同業者が動くのも分かった。
「お姉ちゃん、何?」
荒い靴音と、遠藤さんの指示の声、それに対する返事の声。その中でも抱きしめた由良ちゃんが困惑するのは肌で感じ取れた。
誰かが灯したライトの光に、少しだけホッとした。
でも、その安心はすぐに裏切られた。
「ぐぁ……ぁっ」
今までに聞いたことのない声だった。病院勤めの頃に、患者さんが痛みに叫ぶのを聞いたこともあったわ。でも、その声は違った。
とっさに思ったのは、護衛の誰かがやられたということ。
そして、次は自分だと確信して、ぎゅっと身体を強張らせた。相手の武器はナイフ。それなら筋肉を緊張させれば突き通すのは難しいと思った。腕の中の女の子を傷つけるわけにはいかないって。
周囲を伺ったあたしの目に、信じられない物が飛び込んだ。
誰かの持つライトに照らされて、由良ちゃんのお父さんの胸から、血が、本当に噴き出していたの。血の、鉄さびのような匂いがきつくて、吐くかと思ったわ。手術室勤務をしたこともあったから、自分は血に慣れていると思っていたけど、薬の匂いが混ざらない、純粋な、血の匂いは初めてだった。
あたしは、呆然としながら、それでも、その光景を由良ちゃんに見せないように、抱き締めていた。
「いやぁぁぁっ!」
「お母さん?」
母親の悲鳴を聞き取って、由良ちゃんがあたしの腕を振りほどこうともがいた。でも、あたしは絶対に見せるつもりはなかった。
「ち、っくしょう!」
遠藤さんの悪態に、あたしは違和感を覚えた。
「おい、えーと、安威川! 嬢ちゃんを別室に連れてけ! 説明は後だ!」
違和感の正体を見つけることができないまま、あたしは由良ちゃんを抱きかかえたまま二つ隣の客室に移動する。ちらり、と振り返った遠藤さんの肩越しに、由良ちゃんの母親が胸を押さえているのが見えた。
「お母さんは? ねぇ、お姉ちゃん、お母さんは?」
小さなペンライトを頼りに、私は由良ちゃんを運んで行く。
「うん、後で来るから、由良ちゃんはこっちの部屋で待ってようね」
遠藤さんはどうして由良ちゃんを護衛の薄い別室に移動させたのか、説明とは何のことか、何も分からず混乱していた。
それでも、由良ちゃんにあの光景だけは見せちゃいけないと、それだけは分かっていた。
しばらくして、電源が復旧したのか、邸内に灯りが戻った。
目の前には心配そうにあたしを見上げる由良ちゃんが居た。
「あのね、お母さんは心臓が悪いの。お父さんがいつも背中をさすってね、大丈夫、大丈夫って言うの。由良もいつか、あんな風にお母さんを安心させられたらいいのにね」
お父さん、と無邪気に口にする由良ちゃんに、あたしの良心がズキリと
ぞくり、と震える身体を押し殺す。
「由良ちゃんなら、きっとすぐにできるようになるわ。お姉さんが保証してあげる」
あたしは病院で幼い患者を元気付けるように、そう気休めを口にした。由良ちゃんに慰めの手をかけるしかなかった。
「ねぇ、お姉ちゃん?」
「ん、なぁに?」
「あの声は、……誰の声? すっごく気味悪いの。聞こえた?」
それが父親の断末魔の悲鳴と知らないからこそ、とても残酷な感想だった。
「聞こえたけど、うーん、あたしも暗くてよく分からなかった」
答えながらも、脳裏に焼きついた血の噴水に、思わず口を押さえた。
「お姉ちゃん? どうしたの? 気分が悪いの?}
「ん、ちょっとね。……由良ちゃん、背中、さすってくれる?」
「うん! やったげる!」
由良ちゃんはそう言うと、その細い手であたしの背中を撫でる。
「大丈夫、だいじょーぶ」
撫でると言うより、軽く叩くような形で、ぬくもりがあたしを
いや、違う。震えていたのはあたしだった。
あんなに
手術中にトラブルで勢い良く血が出てしまうことはあったけれど、あそこまでじゃない。あんな状況では、心臓の弱い母親が発作を起こしたのも頷ける。
「安威川!」
「は、はい!」
いつの間にか部屋に来ていた遠藤さんの声に、あたしは慌てて顔を上げた。見れば、由良ちゃんもびっくりして目を丸くしている。
「オレが嬢ちゃんを見とく。安威川は現場へ行け」
「はい? 行ってどうするん―――」
「とにかく状況を把握して戻って来いっ!」
珍しく慌てているのか焦っているのか、遠藤さんの言葉は要領を得なかった。実際は、途方に暮れていたのだと気付いたのは、現場に戻ってからだった。
「おう、来たか。精神安定剤」
遠藤さんの相方の村田さんという人が、あたしをそう呼んだ。そこで、ようやくあたしは今回の計画を説明された。
本当の標的は父親であったこと。あたしの仕事は子守だったこと。
「……なんて、こと」
それがあたしの第一声だった。
最初から
「奥さんの方も、残念ながら……」
あの光景に心臓発作を起こした奥さんは救急車で運ばれている。AEDを使用するも、脈は戻らない。そして、これからも戻る可能性は低い。
あたしは人間の
「問題は、お嬢ちゃんだ。この後、引き取ってくれそうな親類はいるが、本人にどう伝えたものか―――」
「そこで、元看護師のあたしの出番、ということですか?」
「そうだ」
後ろ暗さの
「絶対に
つまり、見知らぬ男達の大群に、由良ちゃんが必要以上に脅えないようにとの配慮だった、と村田さんは説明した。
「お前の昔取った杵柄が役に立つんだ。役立たずよかマシだろ」
一切飾ることのないキツい一言に、あたしは涙をこぼさないように「分かりました」と答えるのが精一杯だった。
そう、あたしが泣いてちゃいけない。
パシン、と両手で頬を叩く。
父親も母親も病院に運ばれ、ここに残るのは血の染み込んだ絨毯と、踏み荒らされた血の足跡。
「おい、こらっ」
パタパタと軽い足音が近づいて来るのが聞こえ、あたしは慌てて扉の方に向かった。せっかく落ち着いた心拍数が一気に戻る。
この邸で、そんな足音を立てるのは一人しかいない。
「お姉ちゃん、こっちに居るの?」
無邪気な声が廊下から聞こえる。
そして、ドアを閉めようとしたあたしの手は間に合わなかった。
「うそ、……なに、これ。―――や」
ぐらりと小さな身体が傾く。その視線の先には、あちこちが血に汚れたダイニングルーム。
「や、あ、あ、あ」
由良ちゃんの顔が恐怖に歪み、下唇が震える。
「あ―――――っ!」
小さな頭は目の前の光景を処理し切れず、絶叫がこぼれる。
そのまま気を失ってしまった由良ちゃんは、二十四時間眠り続け、その間に全てが終わった。父親も母親も死亡と診断され、叔母にあたる人が迎えに来た。
でも、由良ちゃんは現実を受け入れることができなかった。
あたしや親戚の人の説明を聞いても信じず、ぷつり、と何かが切れてしまったかのように世界を閉ざしてしまったのだ。
契約が切れた後に、何度も見舞いに来たけれど、由良ちゃんは他人の言葉に反応せず、ただ食事と排泄と睡眠を繰り返すだけの人形のようになってしまったのだ。
それから一年、別件で遠藤さんと組んだときに、彼女が「戻って」来たという話を聞いた。
けど、あたしは許せなかったし、今でも許せないと思ってる。何もできなかった自分と、……キラー・ショウを。
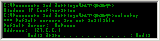
「なるほど、な」
苦いばかりでイマイチだ、と言うティーバッグのお茶を含みながら、今回の暗殺対象である悟が相槌を打った。
「それで、頭は冷えたか?」
始終冷静に、キラー・ショウの最後の仕事ぶりを聞いていた悟少年の言葉に、摩耶は嘆息した。
「君も、よくこんな話を聞けるわね」
「……? 今度こそ守るつもりなんだろ?」
にやにやと意地の悪い笑みを浮かべて、彼が皮肉を口にする。
(こん、のクソガキゃ~!)
心の中でギリギリと
「でも、本当にこうやって逃げるだけじゃ……何よ?」
皮肉を無視して話題を変える摩耶を見ながら、悟はニヤニヤとした笑いを消そうともしない。
「いや、今までの護衛は加害者との直接対決しかなかったんだろうな、と思って」
「どうせ、頭脳労働は得意じゃありません!」
「そう、僕の得意分野だ」
誇らしげに自分を指した悟に、摩耶は相手の年齢を忘れて「何か策があるの?」と尋ねた。
「もちろんだ。雇われているヤツが動かないなら、雇用主を叩く。ハイリスクだが、ずるずると長期戦が続くよりはマシだ」
悟は、とびっきり意地の悪い笑みを浮かべた。