13.道は近きにあり
「そう、やっぱり喘息が悪化したの……」
「まぁ、親から引き離されたストレスもあったんじゃねぇの? 精神的なもんがトリガーになることって、あるんだろ?」
「えぇ。……あたしが言えた義理じゃないかもしれないけど、ありがとう。由佳里を助けてくれて」
摩耶は膝に頭を乗せて眠る娘の頭を撫で、かつて敵だった男に頭を下げた。
コタツで三人和やかに夕食を取った後、ずっと摩耶に引っ付いていた由佳里は、コテンと横になって寝てしまっていた。
昇から娘の様子を聞きながら、何度目かの感謝を口にした摩耶は向かいに座る彼を見つめた。
「羽谷さんは離職するって聞いたわ。あなたは、これからどうするの?」
「え? オレ? まぁ、またテキトーに職を探すと思うけど?」
「アラサーの男性から『テキトーに職を探す』とか言われると、何だかイラッとくるわね」
だいたいアラサーの男が女装なんて、とぶちぶち呟く摩耶に、昇は苦笑を浮かべた。
「確かに、そろそろ真っ当な職に就きたいとは思うけど、ホントの名前では職歴がないのがイタいんだよなー」
職歴がなくても「羽谷」の仕事ぶりを考えれば、引く手数多だと思うのは自分だけだろうか、と摩耶は考える。
「何? そんなに見つめちゃって。オレのこと気になる?」
羽谷ともあの美女とも違う、くりくりとした目に、思わず詐欺だわ、とジト目になるのは仕方がない。
「えぇ、気になるわ。由佳里が世話になってるし、懐いてるし、連絡が取れるようにはして欲しいもの」
少なくともドロンと消えるのだけは止めてほしい。何せ、由佳里の言う「パパ」なのだから。「パパ」に会えなくなったら、由佳里が悲しむのは目に見える。
「うわー。由佳里第一主義かー」
「そもそも『パパ』って何よ、『パパ』って」
「いや、最初は『お兄ちゃん』だったんだけど、授業参観に行ってから『パパ』になっちゃったんだよね。『お父さん』とは違うから『パパ』だって」
お父さんとは違う、という言葉に、摩耶は大きなため息をついた。
「なんだ? 由佳里の父親とよりを戻す予定でもあるのか?」
「まさか。冗談言わないで。アレとは完全に切れてるわ。―――由佳里も見つかったし、看護師に戻ろうとは思っているけど、同じ病院には戻らないから」
「じゃ、なんでさ、そのため息」
「……ちょっと、心の傷になっちゃったかなって。心配……そう、心配なだけ」
子供特有の柔らかい髪を何度も撫でる。
大人になってからの四年間と、子供の四年間は随分と違う。その貴重な四年を、不安な思いで過ごさせることになってしまったのだ。
「大丈夫だよ。ちゃんとお母さんと暮らせるようになったんだし」
「あなたのその自身がどこから来るのか不思議だわ」
「アンタが心配性なだけだろ。由佳里はそんなに弱くねぇよ」
まるで、目の前の男の方が娘のことをよく分かっているような気がして、再び摩耶はため息をついた。
「あなたのその性格が伝染ったのかしら」
「何気にひでぇな、アンタ。そーゆーところは由佳里もよく似てる」
「そう?」
「あぁ、だからむしろオレが由佳里に助けられた」
昇の言うことが分からず首を傾げると、彼はそっぽを向いた。
「水上由良の件があって、オレ、すっげぇ腐ってたんだよ。成り行きで由佳里を拾ったけど、……まぁ、アレだ。オレの方が由佳里に色々と教えられた」
「由佳里が? だってその頃はまだ六歳でしょ?」
もっともな摩耶の問い掛けに、昇はちらり、と眠ったままの由佳里の頭を見た。
「あぁ、でも、オレにない優しさとかあったかさとか持ってたよ」
ぼそり、と呟くように答えた内容に、摩耶は何となく「あぁ」と同じぐらい小さく頷いた。
詳しく追及して良い話ではないだろうが、何となく「殺し屋」なんてことをしていた彼には、とんでもなく大事な何かが欠けていたんだろう。それを由佳里が埋めたというなら、それも何となく分かる気がした。
そう、全て「何となく」。
推測が合っているかも分からないし、わざわざ答えを照らし合わせる気もない。そういう「何となく」だ。
それならば、目の前の「テキトー」な男に言うべきセリフも分かった。「何となく」。
「行く当てがないなら、しばらくここに住む? 世帯向けの間取りだから、部屋も余ってるし、そうすれば由佳里も喜ぶわ」
彼の言う「由佳里第一主義」の自分からすれば、妥当な提案だろうと思った。
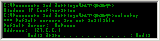
「そうか、看護師に戻るんだ」
「えぇ、正直なところ、あまり今の職は向いていないと思うから」
「まぁ、短絡思考なお前には向いてないだろ。戦略のせの字もないからな」
「言ったわね」
正式な報告書を提出するついでに顔を出せば、悟は快く迎えてくれた。
引継ぎや何やらで祖父もなかなか帰って来れないらしい。だが、寂しがっている様子はなかった。
(ま、悟くんのことだから、思ってても表に出さないと思うけどね)
「来週から学校に戻るんだ」
「あぁ、そうか。毒殺騒ぎがあってから、ずっと休んでいたんでしょう? 授業についていくのが大変―――そうには見えないわね」
「僕をバカにしているだろう、お前」
軽口を返しながら、少しだけ考え込む様子を見せた悟に、摩耶はこの後の誘いをするか、ちょっとだけ悩んだ。
(ま、誘わないよりはいいか)
この大雑把な考え方が悟に「戦略のせの字もない」と言われる原因なのかもしれないが、摩耶には今更自分の性格を直す気はないし、直す必要も感じてない。
「ねぇ、良かったらうちの子と会う? さすがにここに連れては来れなかったけど、近くまで一緒に来たの。君のこと話したら会ってみたいって。―――彼も一緒にいるわ」
彼、という言葉に目を丸くした悟は、しばらく視線を泳がせ、そして頷いた。
―――邸を出た悟と摩耶が向かったのは、ほど近いグループ系列のホテルのラウンジだった。
「お母さん!」
満面の笑みを浮かべて手を振る由佳里の隣に、苦笑を浮かべる昇の姿がある。悟の知る羽谷と背も顔も同じ。だが、いつも七対三だった髪はくしゃりと無造作にスタイリングされ、身につけているのもスーツではなくラフなトレーナーとジーンズだった。
「ただいま、由佳里。良い子にしてた?」
「うん!」
抱き合う母娘とは対照的に、微妙な距離感の昇と悟。
「えぇと、初めましてってことでどうかな、悟ぼっちゃん?」
「ぼっちゃんはやめろ。……初めまして、だな。笹木さん?」
何故か堅苦しく握手を交わす二人を横目に苦笑すると、由佳里が悟に向き直った。
「初めまして、悟くん、だよね? 安威川由佳里って言います」
少し緊張した様子でぺこり、とお辞儀をした由佳里は、自分も握手するんだと右手を差し出した。
「初めまして」
求められるがままに右手で握手した悟に、由佳里はにっこりと微笑んだ。
「あのね、お母さんから聞いたよ? すっごく頭が良いんだって!」
「頭が良い、ね。そのフレーズは久々に聞いたな」
フレーズ、という聞きなれない単語に首を傾げた由佳里は、「あぁ、やっぱり頭が良いんだ」と一人納得する。
その様子を眺めながら、摩耶は寄って来たウェイターに飲み物を注文した。
「頭の良い人は学者さんになるんだって、同じ組のヨウくんが言ってたよ。悟くんも学者さんになるの?」
「あら、由佳里、ちゃんとあたし言ったじゃない。悟くんはおじいちゃんがやってるお仕事の跡継ぎだって」
摩耶の何気ない指摘に、悟は苦笑して手を振った。
「いや、グループは継がない。いや、継げない」
「え?」
「爺さんから、早川グループには今後一切関わるなって釘をさされたんだ」
あの言葉がまだ消化できずに、悟の視線が自然と下に向く。浮かんだ表情を読み取った昇は「そりゃ複雑な」と心の中でボヤいた。羽谷として悟を見て来た昇は、祖父の役に立とうと頑張っていた少年をよく知っていた。だからこそ、関わるなと言われたなら、さぞや―――
「じゃ、学者でもいいみたいよ、由佳里」
「は?」
その言葉に、間抜けな声を上げた悟だけでなく、昇も発言者=摩耶を見つめた。
「え? だって無理に継がなくてもいいんでしょ? 正直なところ、悟くんだったら、このまま行けば起業もできると思ってたし、パソコンがあんなに強いんだったら、そっち方面で起業したっていいんじゃないの? ついでにそこのテキトー男を雇ってあげてよ」
「お母さん! テキトー男じゃなくてパパ!」
同居してから何度も同じ指摘をし続ける娘は、一向に直らない呼び名に怒って母親の膝の上に乗った。
「はいはい、由佳里は本当に頑固ね。そこの昇パパを雇ってあげて」
昇パパと呼ばれた男は、やれやれ、と肩をすくめた。
「
「は、無理に、か。はははっ……」
力なく笑った悟の目から、ぽろり、と涙がこぼれた。ついでに鱗も落ちた。
祖父の敷いた夢のレールがなくなり、途方に暮れていた。
真っ白な霧の中でどこに向かえばいいか分からなくて立ち止まっていた。
それが、違ったんだ、と思い知らされた。
レールなんてなくても、どこに行ってもいいんだと。
「由佳里の将来の夢はー?」
悟の涙に気付かないまま摩耶は、腕の中の娘に尋ねる。
「一位は、看護師さんでね、二位は女医さん! それで、三位はきゃび、きゃび……」
「キャビンアテンダントだろ?」
「そう、キャビンアテンダント! 四位はパティシエさん」
三位の職業名を口にして導いた昇は、続いたパティシエという単語に、由佳里の作った真っ黒ホットケーキを思い出して苦い顔をする。
だが、母親の気になったのはそこではなかった。
「由佳里、キャビンアテンダントなんてよく知ってるわね。飛行機に乗ったの?」
「うぅん? パパがねー、人気の職業は、ナース、スッチー、キャバジョウって。ナースは看護師さんで、スッチーが、きゃ、キャビンアテンダントでしょ? キャバジョウは由佳里に向いてないんだって」
「ふ~ん……」
それ(男に)人気の職業よね、という意味を込めて視線を向ければ、昇はこっそり悟にハンカチを渡しながら斜め上に視線を泳がせた。
「昇パパには、後でお説教があります」
「そんな、ひでぇ!」
「由佳里に変なことを教えないで!」
言い合いを始めたお母さんとパパに、由佳里はよっこいしょ、と摩耶の膝から降りた。そこで初めて目にハンカチを当てる悟に気付く。
「あれ、悟くん、泣いてるの?」
「あぁ、違う。ちょっとびっくりしただけだ」
「びっくり?」
「うん。由佳里は本当に安威川の娘なんだなって」
無理に継がなくていいと言ったり、将来の夢が順位付けされてたり、悟の固定観念を見事に覆してくれる。
「お母さんの娘だから、似てるのは当たり前よ?」
首を傾げた由佳里の頭を、悟は撫でた。
思えば、あのマンションで擬似家族を装った時も、お互い近い場所で飲み食いしたり、好みを言い合いながら買い物したり、寝る時も隣の寝息や寝言や鼾が聞こえてきたり、悟にとっては新鮮なことだらけだった。たぶん、そんな風に生活していたら目の前の少女のような性格の子ができあがるんだろう。―――自分は、そうはなれないけど。
「安威川と同じ部屋で寝てるのか? だったら、寝言とかすごいだろ」
「うん、昨日はね、『何が攻略手引書よっ!』って怒鳴ってたの。びっくりして起きちゃった」
「攻略手引書……?」
いつの間にか言い合いを止めていた昇が吹き出し、摩耶が慌てた。
「う、うそ、由佳里! あたしそんなこと言ってた?」
「うん、攻略手引書って言ってたよ?」
何故か昇は腹筋を押さえて震えている。
後日、奥山が廃棄しようかどうか悩んでいた羽谷の書類の中に、それを見つけた悟が大笑いするのは、また別の話。