12.暗夜に灯火失う
「すごいことになってるぞ」
正午になってようやく起きた摩耶に、悟は年相応のいたずら小僧のような笑みを見せた。
ネット上は生中継を見た人の反応で溢れているらしく「これ日本?」「やらせじゃね?」など内容の真偽を問うものから、「うわ、イスから落ちた、へっぽこwww」と動揺し切った立川を笑うものなど様々で、それらを確認することで悟の
昨晩は、キラー・ショウを含めた三人で摩耶のマンションに戻って来たのだが、ハッキング等で疲れきった悟が帰り着くなり寝てしまった後に、大人二人はささやかに酒杯を上げていた。
摩耶の傷に触ると言っていたキラー・ショウ=昇だが、自家製のかりん酒を問答無用でグラスに注ぐ彼女を無理に止めることはしなかった。
酒を片手に延々と話していたのは、立川の対応から昇の女装、摩耶の娘のことまで様々な事柄だった。その宴会は夜が白々と明ける頃まで続いていたようで、一向に起きる気配のない摩耶を放置した悟は、早々にパソコンをいじくり情報収集に励んでいた。
「あれ、あの人は?」
「僕が起きた時にはいなかったぞ? まぁ、羽谷のことだから、先に帰って受け入れ準備でもしてるんじゃないのか?」
「あぁ、それもそうね」
―――だが、二人の予想とは裏腹に、戻った邸にも彼の姿はなかった。
「お、お帰りなさいませ」
二人を出迎えたのは、摩耶に「おつかい犬」と称された奥山だった。
「ご無事で何よりです」
たどたどしく言葉を紡ぐと、「会長がお待ちです」と邸の一室に案内しようとする
「え、あたしも?」
「は、はい。安威川様も、ご一緒に、とのことです」
摩耶に話かけられて、ことさらに奥山がびくびくと身を小さくした。脅えられる心当たりがある摩耶は、深くは追及しないことにした。
「羽谷はどうしたんだ? 戻ってないのか?」
悟に尋ねられ、奥山の表情が
「それが……ですね、今朝一番に、離職願いを出したそうです。月末までは籍が残るそうなんですが、溜まっていた有休を消化するとかで」
「なんだって?」
驚きの声を上げる悟の隣で、摩耶は思わず考え込んだ。「羽谷」としての職を捨てるなんて、昨晩飲んでいた時には一言も口にしていなかった。だが、由佳里のことも目処がついたし、と妙に晴れ晴れとした表情だったことが気になる。
「あ、あの、安威川様に、手紙を預かってるんですが――」
恐る恐る差し出す奥山の手から、白い封筒を思い切り引ったくった摩耶は、封を開けるのももどかしく中身を取り出す。
『近い内に、連れて戻って来る。これまでの仕事の後始末をしてから、今度は偽りない姿で』
封筒がもったいなくなるぐらいの短い文章に、摩耶は大きく息を吐いて、隣で見上げて来る悟に手渡した。
「
「そ、そんな、私ではとてもこの邸の采配なんて
摩耶の言葉に泣き崩れる奥山に、
「あ、はい。いつもご使用されている応接に……、って、悟様?」
案内役を振り切って走り出した悟に、摩耶も慌てて追いかける。気を取り直した奥山が追いつく前に、二人はその部屋へたどり着いた。
コンコン
「爺さん、僕だ」
「おぉ、入りなさい」
悟の後ろに続いた摩耶は、幾分緊張してドアを閉めた。
黒い革張りのソファに身を沈めていた老人の所へ、悟が駆け寄るのを棒立ちになって眺めていると、白髭と白髪の老人の目がへにゃり、と柔らかくなるのを目の当たりにして、少しだけ緊張がほぐれる。
「爺さん、ただいま」
「おぉ、悟。よく無事に戻って来た」
もっと鋭い眼光の人ではなかったか、と首を傾げるが、孫の前にはこんなものだろうか、と気を取り直す。
「安威川さん。よく悟を守ってくれた。まぁ、そちらへ腰掛けなさい」
ドアの前で立ちっぱなしになっていた彼女は、「失礼します」と声を掛けて勧められたソファに浅く腰掛ける。
「爺さん。ごめん。僕があんなことをしたから、グループ全体の株価が下がった」
「……やはり、悟。お前の仕業だったんじゃな」
隣で頭を下げる孫に、お前も座れ、と摩耶の隣のソファを示した早川源五郎は、その表情を一変させた。
瞬きする間に、彼の顔が孫を溺愛する
「今回の件、羽谷から報告を受けた。立川の脱税の件と、お前の仕掛けた生放送のことじゃ。元凶は立川だったとは言え、あのやり方は関心せん。報道こそないものの、耳の早い者は市場からケツをまくっておる。株価もじわりじわりと下がっておるようじゃ」
もう少し穏便に済ませて欲しかったというのも本音じゃ、という言葉に悟が
「気が付かなかった儂にも責任はある。―――会長の座から退くことにした」
「爺さん!」
「後任は水島じゃ。今日の十八時に正式に発表する運びとなっておる」
「爺さんのせいじゃない」
「いいや、儂の監督責任じゃよ」
しばらく、祖父と孫が睨み合うように視線を交わした。
折れたのは、孫の方だった。
「―――あの、人の良さそうな観光分野を取り仕切ってるおじさん、なら、いいと思う」
「そうか」
株価の下落という
「安威川さん」
「はい」
「
予想していた質問に、摩耶は安堵した。
「あの人が予告してきた殺し屋です。利害の一致があって手を組みました。詳しくは後日書面にて報告させていただきます」
「素性は?」
「知りません」
「今後、悟を狙うことは?」
「雇用主があのような状況です。危険はないとみて間違いないと思います」
「……そうか」
大きく息を吐いた源五郎は、風船から空気が抜けるように、その覇気を薄れさせた。思わず摩耶も詰めていた息を抜く。
「系列の病院に連絡する。精密検査を受けるように」
「……え?」
「聞こえんかったか? 頭を殴られたのじゃろう、きちんとした検査をせい。すぐに車を回させる」
「お気遣い、ありがとうございます」
手で退室するように指示された摩耶は、立ち上がると一礼し、退室した。
「爺さん……、僕は―――」
「内々にな、警視庁に勤める知人から、お前の両親の事故に立川が関与しているようだと聞いた」
源五郎の言葉に、悟は小さく頷いた。それで、源五郎にも孫がとっくにそれを知っているのだと理解する。
それで、源五郎は、悟の毒殺騒ぎからずっと考えていたことを口にする決心をした。
「悟。お前はグループには一切関わるな」
「爺さん―――」
「血族で固めずとも、会社は動く。お前は、お前のやりたいことをやるがいい」
悟は知っている。
目の前の源五郎が、いつかその地位を息子に譲りたいと思っていたことを。
そして、それが孫にまで繋がれば良いと思っていたことを。
祖父が、悟を、家族を守るために、その夢を曲げたのだ。
「……うん」
これまで、なんとなく祖父の夢のレールの上に乗っていた。
まっすぐ続くと思っていたレールは、両親が天国に行ってしまったことで、その行く先が霧に立ちこめて見えなくなってしまった。
そして今、レールが途切れたのを目の当たりにした。
周囲も分からない霧の中、もはや、どこに向かえばいいのか分からず、途方に暮れるしかなかった。
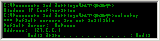
「―――打撲から半日ほど経過しているとのことですが、特に気になる影もありません。ですが、内出血の可能性もありますので、二週間後にまた検査しましょう。それ以前に頭痛や
「はい、ありがとうございました」
指定された病院にて、一通りの検査結果の説明が終わる頃には夕陽が沈もうとしていた。
とりあえず早川邸に連絡して、家に帰って、あ、牛乳終わってたから買わなきゃ、と考えつつ精算に呼ばれるのを待つ。
だが、すぐに名前を呼ばれ、精算せずに帰って良いことを告げられると、改めて早川源五郎の持つ権力に関心する。通常、仕事中の怪我の治療費は後払いが多い。こんなことは初めてだった。
病院を出て、早川邸に連絡しようとスマホを取り出した所で、ドン、と何かにぶつかった。
いや、ぶつかったというのは正しくない。
小学生ぐらいの女の子に抱きつかれたのだ。
迷子に人違いされたかな、と摩耶は「どうしたの?」と女の子の頭を撫でながら優しく話し掛けた。
「お、母さん……」
か細い涙声に、やっぱり迷子か、と納得し、病院の受付に連れて行こうと考えて、止まった。
涙と鼻水でくしゃくしゃになった顔は、自分をまっすぐに見上げている。
「ゆ、かり……?」
「お、かあさん! おかあさん! おかあさん!」
自分の腰ぐらいまでしかなかった身長は、いつの間にか胸のあたりまで伸びていた。髪の毛はあの頃と同じく後ろで一つに結わえている。顔は、……自分の小さい頃にそっくりだった。鼻だけが夫によく似ている。
「由佳里!」
ぎゅっと抱きしめれば、耳元で大声を上げて泣かれてしまった。
無事とは聞いていたけれど、いざ胸に飛び込まれるとついつい
「由佳里、……あの人が連れて来てくれたの?」
「あの人……? うん、パパだよ! パパがね、ここに来ればお母さんに会えるって!」
「―――パパ?」
摩耶の涙が引っ込んだ。
「よ、摩耶ちゃーん。由佳里と一緒に、今夜泊めてくんない?」
由佳里が「パパ」と呼ぶ男は、にこにこと笑みを浮かべて言ってのけた。