10.触らぬ神に祟りなし
(あぁ、くそっ)
広げた雑誌では、厚ぼったい唇の美女が面積の小さい水着を身に付けて微笑んでいた。抱えた浮き輪に圧迫され、形を変えた胸の膨らみが何とも男心をくすぐるポーズだ。
(こんな寒い日に外の夜勤とか、……ツイてねー)
広い邸の正門脇の詰め所は、一畳ほどのスペースしかないにも関わらず、妙に大きな棚が設置されているおかげで、身動きも取りにくい。来客に応対する小窓の近くの椅子に腰掛け、雑誌を読むのが関の山だ。
同じ夜勤でも、邸内の一室でモニターをチェックしてればいいだけの内勤とは
(一度でいいから、こういうオンナとヤってみてーよなー)
胸は大きくなくていい。こう、つやつやぷりぷりの唇で、
コンコン
窓を叩かれ、彼は妄想の世界から現実に帰還する。慌ててガラス戸を開けた。
「こんばんは。門を開けていただきたいのですけれど」
鳥肌が立ったのは、冬の夜の冷たい空気のせいだけではなかった。
彼に呼びかけたのは、まさに求めていた美女。月明かりに照らされているのは、妖艶な笑みを形作る厚い唇。少し、背と肩幅があるのは気になるが、それさえ気にならなくなるほどの色気を湛えていた。
(ショートヘア万歳! うなじ万歳!)
心の中で両手を挙げて叫びながら、彼は真面目な顔を取り繕った。
「残念だが、今は来客を受け入れられないんだ。また後日出直してくれ」
上からの命令そのままに告げると、美女は「あら、困りましたわね……」と頬に手を当てた。その仕草ひとつひとつが、彼の中の何かを騒がせる。
「もし、よければ―――ここに名前と連絡先を」
差し出された紙とペンを一瞥すると、彼の意図を正しく理解した美女の笑みが一層深くなった。
「あら、いけない人ね。お仕事中でしょう? ―――永山、さん?」
胸のプレートに書かれた名前を呼ばれただけで、彼の心臓が激しく脈打った。仕事のフリをして名前と電話番号を手に入れようとしたことはあっさりバレ、さらにやんわりと
(うおぉっ! 「イケない人」とか言われちゃったぜ、オレ!)
イケないとか言われたけど、これだけで三回はイケる。何がとは言わないが。
少しだけ夜勤明けの楽しみに気を取られている間に、目の前の美女が彼の頬に触れていた。
「うぇっ……?」
困惑して変な声が出て焦る。まさか誘われているのかと都合良く解釈して自分の血の巡りが変なことになっているのを感じた。
「ねぇ、悪いとは思いますけれど、急いでいますのよ」
ちくり、という感触に、彼は初めてそれに気付いた。
いつの間にか、美女の手にしたナイフが、彼の首筋に突きつけられていることに。
「ひっ……」
「ねぇ、取り次いでいただける?」
彼はナイフと美女を交互に見ながら、硬直していた。無理もない。彼の命が危険に
「いくじなし、ね」
嘆息した美女は、男の頬に添えられていた手を、彼の胸元に下ろした。ポケットから難なく無線機を取り出すと、六つ並んだボタンを迷うことなく押していく。
「もしもし? いいえ、違いますわ。永山さんではありません。……これから標的と看護師を連れて行くとお伝え願えますか? ―――えぇ、それだけで構いません。荷物を運ぶのに、永山さんをお借りいたしますわね」
まだ何か言い募る無線機越しの相手の声を無視して通信を切ると、会話の間、微動だにさせなかったナイフを引っ込めた。
「そちらに、女一人、子供一人を置いてありますので、運んでくださいません?」
抗う気力もなく、ガクガクと
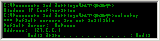
「こんばんは。この頃、夜は冷えますわね」
美女はにこりと微笑んで見せた。
だが対峙する男は至って無表情でその挨拶を流す。目の色を伺おうにも眼鏡のフレームが邪魔して読みきれない。
「いきなりの仕事の変更には驚かされましたけど、まぁ、結果オーライ、ということで」
「……このガキはいつ起きる?」
怨念さえ感じられる声が、部屋に落とされた。意識を失ったまま拘束されている女と少年を運んで来た男は、既に警備に戻っていたので、この部屋には男のボディーガードを含め、5人だけだ。
「お望みでしたら、今でも?」
無言で顎をしゃくった雇い主に、美女はハンカチと香水の小瓶を取り出した。ハンカチにシュッと一噴きさせると目を閉じたままの少年の鼻に押し付ける。五つ数える間もなく、少年の口から小さな唸り声が漏れた。
「なん……だ?」
うっすらと目を開けるや否や、雇い主=立川が少年の胸倉を掴んで持ち上げた。
「このクソガキめ!」
普段の口調をかなぐり捨て、彼の右拳が少年の頬を殴りつける。
「っ!」
張り飛ばされたことで、一気に覚醒したのか、後ろ手に縛られたままの少年は自分を見下ろす男を睨みつけた。
「……ふん、お前の汚いかねが始めて人様の役に立つんだ。ありがたく思って欲しいな、立川のおじさん」
キラー・ショウの元に命令変更が下る前夜、立川が脱税などでせっせと貯めた金をユニセフを筆頭にした様々な団体に勝手に寄付した。さらに嫌がらせとばかりに、立川にその旨をわざわざメールして知らせたのだ。
翌朝、メールに気付き、その内容が真実だと確かめた立川の衝撃は筆舌に尽くしがたいものがあった。
「悟ぼっちゃん。私の要求はただ一つですよ。口座の残高を同等……いや、倍額にしてもらいます」
文字通り一発入れたことで多少の冷静さを取り戻したのか、いつもの口調を取り戻した立川は、確定事項のように告げた。冷め切った声に反して、その瞳には決して消えることのない
「やなこった」
口元を赤く腫らした悟は一言で切り捨てる。
立川は彼に背を向けてマホガニーの机に近寄ると、鍵付きの引き出しから黒く鈍い光沢を持った者を取り出した。オートマチックの銃である。
「この護衛役と姿を消していたそうですね。少しは親しくなりましたか?」
にやにやと笑みを浮かべた立川は、安全装置を付けたままながら、銃口を摩耶に向けた。意識のない彼女は身動ぎ一つない無防備なままだ。
「月並みで申し訳ありませんが、この女の命が惜しければ―――」
「やればいいだろう。元々、僕のボディガードだ。こいつが僕を庇うことはあっても、僕がこいつを
どこか緊張した白い顔で言われて、立川はその言葉を鵜呑みにするほど優しくはなかった。
ちらり、と部屋に立つ自分の使用人と美女に視線を動かし「そちらも起こしなさい」と命を下す。
美女は再びハンカチに瓶の中身を噴き掛けると、それを扉を塞ぐように立っていた使用人に渡した。小さく頷いた使用人が悟の時と同じようにハンカチを口元に当てると、小さく呻いた彼女がうっすらと目を開いた。
「な……に、ここ……」
まだ意識が
「さて、悟ぼっちゃん。意識のある本人の前でもう一度答えてください。この護衛の女性を見捨てると?」
彼女にも見えるように銃口を向け、安全装置に指をかける。
キチリ、という音にようやく覚醒した摩耶の表情が強張っていくのが見えた。
「う、……そ」
「嘘ではありません。悟ぼっちゃんが私の要求を飲んでくれないのであれば、―――仕方がないでしょう?」
「待て! ……分かった。倍額でいいんだな」
「えぇ。初めから聞き分けてくれればよろしかったんですよ」
ようやく自分から離れた銃口に、摩耶だけが現状を把握できず「何の話、なの?」と呆然と呟く。
「貴方は知らなくても良いことよ」
「あ……、あなた!」
ようやく室内を伺う余裕を持てた摩耶が、初めて美女の存在に気付いた。
「よくも人を騙してくれたわね! もう仕事はイヤになったって言っていたくせに!」
「あら、心外です。人を
摩耶が睨みつけてもどこ吹く風の美女=キラー・ショウは優雅に口元に手を当てて笑った。
「だいたい何なのよ、その恰好! あなたホントは―――」
「お黙りなさい」
果たしていつ、どこから取り出したものか、まるで魔法のようにキラー・ショウの右手に現れたナイフが、摩耶の喉下に突き付けられた。
「おや、その続きに興味はあったのですが、仕方がありませんね。本人の前ですから」
立川は残念そうに呟くと、悟に向き直った。
「さて、早速始めてもらいましょうか、悟ぼっちゃん」
少年は、年相応に悔しげな顔を浮かべ、歯を食いしばった。